ここから本文です。
花豆かんさつにっき(1)
博物館活動センターは、花壇で札幌にゆかりのある植物を植えて、ワークショップとして観察をしたり、収穫した実や茎を工作の材料にしたりしています。
この「花豆かんさつにっき」では、花豆に注目して、どんなふうに育っていくのか、みなさんといっしょに見ていきます!
今回は第1回目!タネまきのようすを紹介するよ!
そもそも花豆(ハナマメ)って?
ここまで、「花豆」と書いていたけど、本当は「ベニバナインゲン」や「シロバナインゲン」って名前だよ。海外から日本にはじめて入ってきたときには、豆ではなく、きれいなお花が注目されていたんだ。
明治時代(150年くらい前)に、札幌の畑でうまく育つかどうかを試してみたら……大成功!
花豆は夏に涼しいところが得意な植物なので、北海道で育てるのにぴったりだったんだ。
※花豆の原産地は南米の高地とされています。
今では、日本で一番多く花豆をつくっているのは、北海道なんです!
花豆かんさつにっき1ページめ
日付:2023年5月13日(土曜日)
天気:晴れ
気温:23℃
場所:博物館活動センターの花壇
今日は、ミニ・ワークショップ「花豆のタネをまこう」でハナマメのタネをまいたよ!
 |
まずはハナマメがどんな植物なのか、学芸員の解説を聞きました。 |
 |
ハナマメのタネは、まさしく豆そのもの! |
 |
山崎学芸員のまき方のお手本を見ながら、ふかふかの土の中にハナマメのタネをまきました。 穴の深さは8cmほど。 |
 |
土をかけた後、ぎゅっぎゅっと押すのがタネまきの基本ポイント! タネと土がくっつくようにすることで、うまく芽が出やすくなるよ。 |
 |
たまにカラスやハトがタネを掘り返して食べてしまうそう……。
芽が出るまでは1週間ぐらいかかるよ。それまでスタッフがこまめに水やりをするよ。 |
最後に、参加者のみなさんにメッセージカードを書いてもらいました!
看板にして花壇に立てたので、観察する際はぜひみてね!
※ベニバナインゲンとシロバナインゲン:同じハナマメでも色の違いで呼び分けているよ。
藍(アイ)
ハナマメと一緒に、藍(アイ)のタネもまきました。
タデアイとも言い、藍染めの原料です。
「藍染め」は、アイの青系の色素(色のもとになるもの)を使って、布や糸を染めることだよ!
 |
まずはアイの歴史について勉強中……。 明治時代に、札幌でアイの栽培に挑戦した人たちがいたんだよ! 今も「あいの里」の地名として残されています。
|
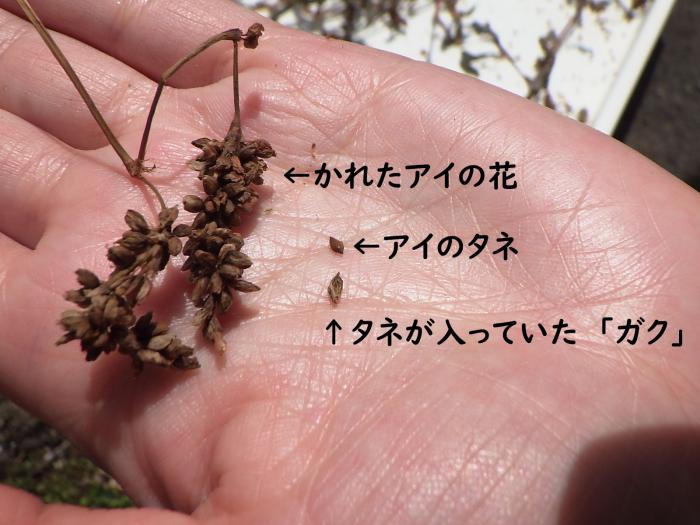 |
去年(2022年)に育てたアイからとったタネ。 |
 |
土に指でミゾを付けて「すじまき」にしたよ。 |
※パンフレットは北区役所から提供いただきました。
アイについては、北区のホームページに詳しく載っています。ぜひご覧ください!
北区役所ホームページ(北区の藍栽培の歴史伝承について載っています)
「かんさつにっき」ワークシート
ワークシート(PDF:97KB)をダウンロードして、みんなもかんさつにっきを書いてみよう!
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.
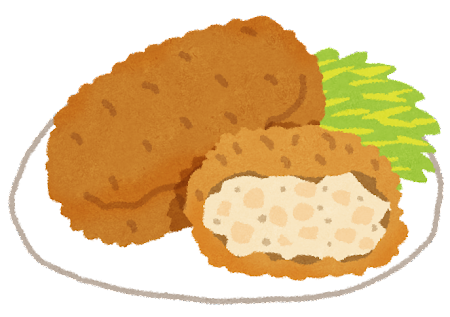
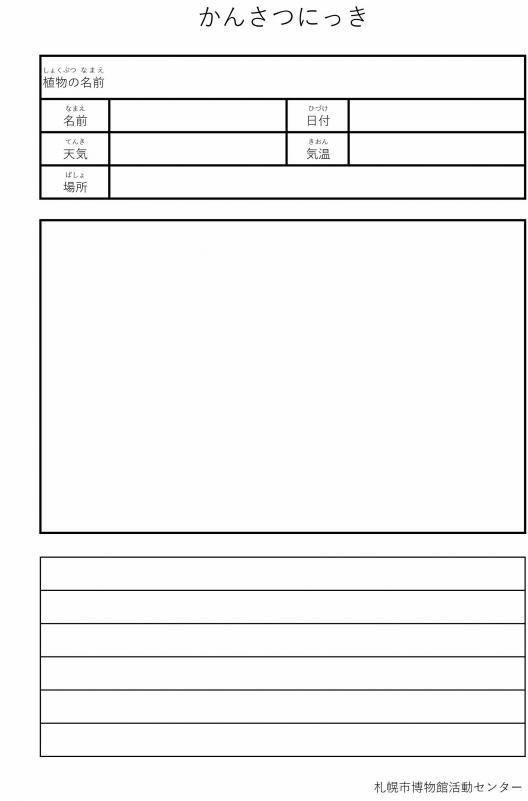 (PDF:97KB)
(PDF:97KB)