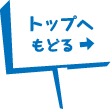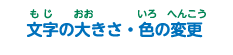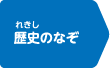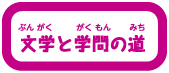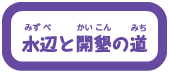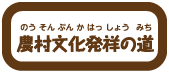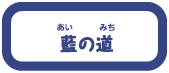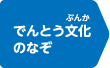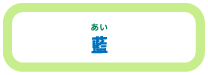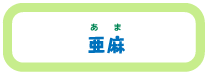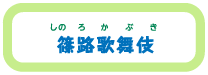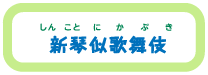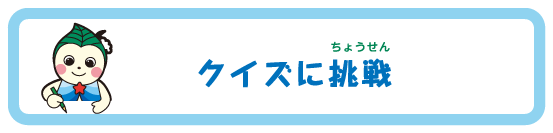ここから本文です。

藍は、藍染めのせん料となる植物で、世界各地で古くからさいばいされています。
北区の藍の歴史は、明治15年(1882年)、徳島県の滝本五郎を中心とする一だんが篠路村にやってきたところから始まります。
滝本たちは、大へんな苦ろうをしながら、あれた土地を切り開いて農地を作り、そこに大豆やソバ、トウモロコシなどのほか藍を植えました。その中で、さいばいにせいこうしたのが藍でした。藍を植えたのは、出身地の徳島県が藍の特さん地であったことや、藍さいばいのひりょうに使うニシンかすが、石狩の浜が近い篠路で手に入れやすかったことなどが理由でした。
滝本は、藍の葉を加工して「すくも」というせん料を作り、全国にはん売しました。売り上げはどんどん伸び、藍さいばいはますますさかんになっていきました。
その後、外国の安いせん料などの進出により、藍さいばいは少しずつおとろえていき、やがてさいばいされなくなってしまいましたが、この藍の歴史は今でも「あいの里」という地名や「英藍高校」の名前となってのこっています。
昭和59年(1984年)ころから、篠路に住む人たちが中心となって、「藍染め」という形で、北区の藍さいばいの歴史をつたえる取り組みが始まりました。げんざい、このような地いきの人たちと北区役所がきょう力して、小学校で藍さいばいの歴史を伝える授業を行ったり、区みんに藍のたねを配ふしたりしています。