災害に備える(自助・共助) > 企業の防災 > 4.(2)安全を守る「体制」づくり
ここから本文です。
4.(2)安全を守る「体制」づくり
被害を最小に抑える(減災)ためには、「人」「モノ」「情報」「資金」の4つの経営資源を活用・保全できる体制を整えておく必要があります。
1.組織体制(人)
役割分担を明確にする
業務時間内に災害が発生した際は、職場にとどまり、緊急対応をするのに必要な人員を確保するほか、夜間・休日の場合を想定した体制もあらかじめ決めておきましょう。
本社が札幌にない場合は、支店で意思決定できる体制をつくるなど、自社に合った形で役割を振り分けましょう。
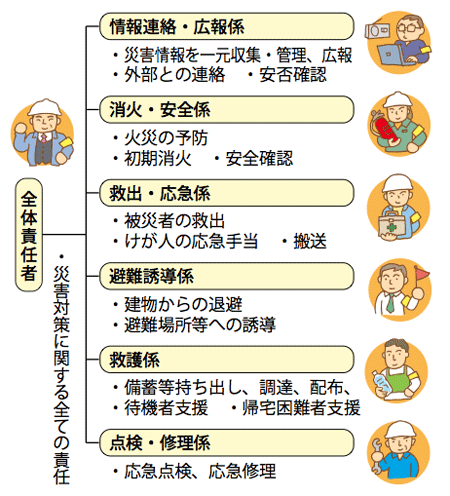
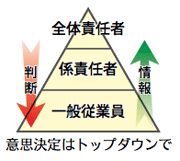
テナントビルでも役割分担

テナントビルなどの複数の事業者が入居する建物では、責任の所在が不明瞭なため対応が遅れ、被害が拡大することも想定されます。ビルオーナーと事前に相談し、共用部分の安全確認、避難路の確保、避難誘導、初期消火などの手順や役割分担などを、テナント間で事前に確認しておきましょう。
こうした現象を防ぐために、それぞれの責任を明確にすることが大切です。安否確認、誘導、備品配布など、役割を細分化して割り当て、日ごろから役割を認識し責任をもって行動できるよう工夫しましょう。
2.建物の安全、備蓄(モノ)
安全な労働空間づくり
机や棚、什器、パソコンなどは転倒防止対策を行い、被害を軽減するような配置に気をつけましょう。コピー機などキャスター付きの物は固定します。また、陳列棚や窓のガラスの飛散防止対策を行い、落下しにくい照明を採用するなど、利用客への安全対策も大切です。工場などでは、機械の安全対策について、技術者やメーカーと方法を検討しましょう。
転倒防止などの工夫の例
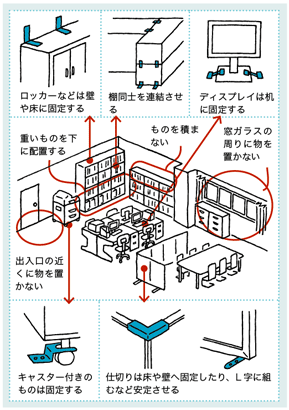
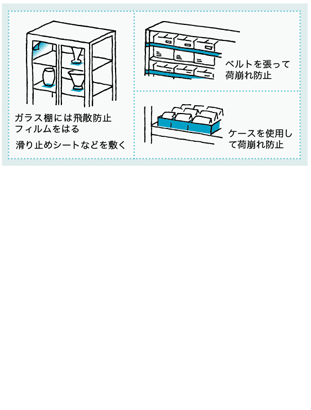
建物の耐震化を進める
建物の耐震性を把握し、被害を軽減できるよう、必要な対策を行いましょう。札幌市では、建物の耐震化にかかる費用の一部を補助しています。対象は、昭和56年5月31日以前に建築された私立学校、社会福祉施設、病院、分譲マンション、緊急輸送道路沿道建築物、収容避難施設です。
補助制度の内容や手続き等の詳細については、下記までお問い合わせください。
電話:011-211-2867
FAX:011-211-2823
http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/taishin/shindan.html
備蓄する
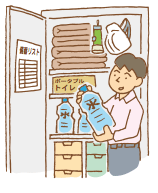
非常時に備え最低3日分の備蓄をしましょう。帰宅困難者の受け入れを想定し、多めの備蓄をします。冬の寒さ対策として防寒用の毛布やシートも用意しましょう。
また、保管場所や資材の共同利用など、地域や近隣企業と連携した対策を検討するとよいでしょう。
企業での備蓄の例
| 飲料 | 飲料水、非常食、缶詰、保存水(一人1日3L)、給水タンク、紙皿、ラップなど |
|---|---|
| 医薬品 | 殺菌消毒薬、火傷薬、整腸剤、絆創膏、包帯、ガーゼ、脱脂綿、タオル、ピンセット、三角巾など |
| 救助資材 | 担架、工具(のこぎり、バール、ハンマー、スコップ、ジャッキ、つるはし)、ロープ、照明、はしごなど |
| 避難資材 | 懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、ろうそく、ライター、マッチ、炊飯器具、拡声器、無線など |
| 防護資材 | ビニールシート、ヘルメット、軍手、安全靴など |
| その他 | ビニール袋、簡易トイレなど |
3.連絡体制
安否の確認方法を決めておく
安否確認を行う責任者を決めておきます。通話規制や輻輳(ふくそう)により電話がつながりにくくなるため、電話以外の方法も想定しておきましょう。災害用伝言サービス、携帯電話のデータ通信、インターネット(各種ネットサービス、ミニブログ、掲示板など)、安否確認サービスなどの活用を検討しましょう。
伝言は最小限に
伝言は最小限必要な、現在地、被害の有無、移動場所、家族の安否などの事項にとどめます。
家族との安否確認も大切
従業員と家族の間の安否確認も大切です。災害対応に専念する従業員のために、家族の安否を企業が確認して伝えるなど、安心して災害対応に専念できる環境を整えましょう。また、従業員も、各電話事業者による災害用の伝言サービスを利用するなど、あらかじめ家族と連絡方法を決めておきましょう。
緊急連絡網と複数の情報窓口を用意する
従業員の安否確認や企業の指示を伝えるため、緊急連絡網を整備しましょう。また、社屋などが損壊した場合の情報収集や発信の代替窓口も検討しておきましょう。
情報の収集、発信方法を決めておく
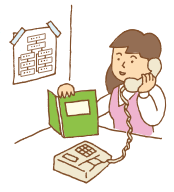
全体責任者は全ての情報を一元化し、対応を決定する必要があります。意思決定に必要な情報の種類(人的被害、自社の被害、地域の被害など)、情報の入手方法や収集担当者を確認しておきましょう。
また、帰宅困難者へは地域の被害情報を掲出して知らせます。外部へはインターネットなどを活用して自社の被害や今後の見通しを伝えます。
情報収集の項目例
| 人的被害 | 利用客や従業員の被害状況 従業員の家族の被害状況 |
|---|---|
| 自社の被害 | 建物・設備・配管など、生産手段、通信、情報システム、商品や仕掛品の状況、危険物や有害物の状況、立入禁止箇所の有無 |
| 地域の被害 | 周辺の人的被害や建物被害、道路状況や交通規制、公共交通の被害、取引先など関連企業の状況 |
緊急連絡先の例
- 近隣医療機関
- 消防
- 設備保守業者
- 顧客
- 取引先
4.対策費(資金)
被害軽減のための費用を確保する
建物や設備の耐震化、備蓄、人材育成など、地震対策を進めるためには資金も必要です。いつ起こるか分からない地震の対策費はムダに思えるかもしれませんが、企業の責任として、必要な措置について優先順位をつけて取組を進めましょう。
地震対策費とコスト
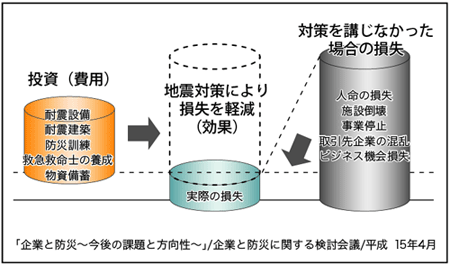
はじめに|1.札幌でも大地震が起こる・・・|2.企業で想定される大きな被害|3.防災協働社会を目指して|4.企業の安全を守る|5.地域の安全に貢献する|6.企業活動を継続する|7.企業全体で高める防災力|8.お役立ち参考資料
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.