ホーム > くらし・手続き > 動物・ペット > 鳥獣(野生動物等)など > ヒグマ対策 > 札幌市の課題と対策
ここから本文です。
札幌市の課題と対策
札幌市のヒグマ対策における現状の課題と対策について紹介しています。
令和7年「人里出没抑制等のための春期管理捕獲」事業の実施
札幌市では、人里周辺でのヒグマの出没抑制とヒグマ対策に必要な人材の育成を目的に、北海道が進めるヒグマの「人里出没抑制等のための春期管理捕獲」事業を行っています。今年も以下のとおり事業を行いますので、お知らせします。
猟銃を持ったハンターが区域内を踏査いたします。状況によっては発砲する場合もあり大変危険ですので、閉鎖期間中は区域内の入林を禁止とさせていただきます。何卒ご了承願います。
実施区域
自然歩道「中の沢~小林峠・源八沢ルート」、白川市民の森、三角山周辺(自然歩道「三角山~盤渓ルート」周辺)、その他国有林など
※詳細は実施区域図をご確認ください。
実施区域図(自然歩道、白川市民の森、その他国有林など)(PDF:504KB)
各区域の閉鎖期間(予定)
- 自然歩道「中の沢~小林峠・源八沢ルート」、白川市民の森
令和7年3月1日(土曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
- 三角山周辺(自然歩道「三角山~盤渓ルート」周辺)
令和7年3月16日(日曜日)8時00分~17時00分
令和7年3月23日(日曜日)8時00分~17時00分
- その他国有林など
令和7年3月1日(土曜日)~令和7年4月30日(水曜日)
札幌市の地理的特徴と土地利用状況の変化
札幌市は、市域の約6割が森林で占められており、豊かな自然に囲まれた大都市です。同時にこの森林には、多くのヒグマが生息しています。
札幌市には、人口密度の高い市街地とヒグマの生息する森林とが直接つながっている地域が多く、ヒグマの森林から市街地への侵入を防ぐための「緩衝帯」となる地域が少ない、という地理的特徴があります。
さらに近年、地主の不在等の理由で、管理がされず、草木が生い茂ってしまっている土地や、放棄されたままになっている果樹が増えてきています。もともと「緩衝帯」となっていた地域が、その役割を果たせなくなってきていることが、ヒグマが市街地に侵入したり、ヒグマを市街地の近くに誘引したりする要因の一つとなっています。

果樹や作物の管理について
放棄されたままになっている果樹や作物は、ヒグマを誘引し、人が作った食べ物の味を学習させてしまうため、ヒグマが家庭菜園の作物を求めて市街地に出没するきっかけとなってしまう場合があります。
ヒグマが出没する可能性のある地域では、必要の無い果樹は伐採する、伐採できない場合には果樹を電気柵で囲う、実っている果実を早目に収穫するなどの対策が必要です。
また、森林に近接する家庭菜園の作物についても、電気柵で囲うなど、ヒグマを誘引しないための対策が必要です。札幌市では、ヒグマを市街地に侵入させないための取組みの一つとして、家庭菜園向けの電気柵の購入補助及び無償貸出しを行っています。
草地の管理について~草刈りの重要性~
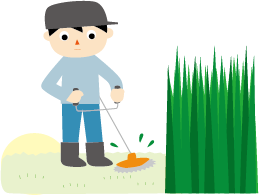 |
ヒグマの出没を減らし、市街地への侵入を防止するためには、 市街地と森林の間に「緩衝帯」を確保することが重要です。 ヒグマには、開けた見とおしのいい場所を避け、藪などで身を 隠しながら行動する特性があることから、市街地と森林との間に ある草地や市街地につながる河畔林など、ヒグマの侵入経路と なり得る場所の木や雑草を刈り取って見とおしをよくすることで、 ヒグマの出没を減らすことができます。 札幌市には、市街地への侵入経路となる可能性のある場所が 複数あるため、地域全体で一体となってヒグマが出没しにくい 環境づくりに取り組んでいく必要があります。 |
札幌市における草刈り事業
石山地区
南区石山地区の豊平川石山大橋付近では、平成24年、25年にヒグマが出没したことを受けて、平成26年から、「石山地区まちづくり協議会」と「浦幌ヒグマ調査会」(事務局:酪農学園大学)が中心となって、毎年8月に河畔林の下草を刈っており、ヒグマの出没抑制に効果をあげています。
令和元年度は、8月3日(土曜日)に行われ、石山地区の住民や酪農学園大学の学生など、約60人が参加しました。草刈り終了後には、酪農学園大学の学生がヒグマに関する研究や調査について報告する「ヒグマ勉強会」や「ビンゴ大会」が行われるなど、地域住民同士の交流の場にもなっていました。
|
草刈りの様子 |
ヒグマ勉強会の様子 |
藤野地区
令和元年8月30日(金曜日)、地域の課題を考える総合学習の一環で、「ヒグマ問題」をテーマに選んだ市立札幌藻岩高校の学生8人が、南区藤野地区の野々沢川で草刈りを行いました。草刈りを行う直前のガイダンスでは、市民一人ひとりが「ヒグマとの共生」のためにできることについて、市の担当者とで意見交換を行い、ヒグマの問題行動を予防するために、草刈りや電気柵の設置が有効であることを学びました。
|
草刈り前-1 |
草刈り後-1 |
|
草刈り前-2 |
草刈り後-2 |
生息状況の変化
かつて北海道では、昭和41年から行われていた残雪期のヒグマの駆除事業「春グマ駆除」により、積極的なヒグマの駆除が進められました。その結果、個体数の著しい減少が懸念されたため、春グマ駆除は平成元年度に廃止され、その後は保護に重心を置いた施策が実施されました。
現在、札幌市を含む石狩西部(積丹・恵庭地域)のヒグマは、環境省レッドリストで「絶滅のおそれのある地域個体群」に指定されていますが、一方で、最新の調査では、石狩西部のヒグマの個体数が増えてきている可能性が示されています(「ヒグマ推定生息数(R2年度)」北海道)。
生息状況の把握
札幌市は、石狩西部のヒグマ個体群の保全とあつれき防止とを両立しながら、ヒグマと共生していくことを目指しています。その前提として、ヒグマの生息状況や出没状況を把握するため、調査研究や継続的なモニタリングを行うことが重要となります。
平成27年度札幌市ヒグマ生息基礎調査
札幌市では、平成27年度に「さっぽろヒグマ基本計画」策定の基礎資料として、道立総合研究機構及び酪農学園大学と共同で「ヒグマ生息基礎調査」を行いました。
関連リンク:「平成27年度札幌市ヒグマ生息基礎調査」の結果
令和2年度ヒグマ生息実態調査
札幌市では、令和2年度に、平成27年度から5年ぶりとなる「ヒグマ生息実態調査」を実施することとしています。市内におけるヒグマの生息状況について、前回の調査結果との比較を交えながら分析します。
捕獲従事者の減少と高齢化
近年、ヒグマ出没に対応できる熟練した捕獲従事者の減少及び高齢化が進んでおり、将来的な人材不足が懸念されています。
また、春グマ駆除廃止以降、保護に重心を置いた施策が実施される中で、捕獲従事者の減少と高齢化により、ヒグマへの捕獲圧が緩んだことが原因と考えられる、人への警戒心が希薄で、人を恐れないヒグマの出現も見られております。
ヒグマの生息状況が変化し、市街地での出没件数も増加傾向にある中、ヒグマを市街地に侵入させない対策を進めるとともに、ヒグマ捕獲の経験と技術を有する従事者の育成が課題となっています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.





