ここから本文です。
さっぽろ市議会だよりNo.123
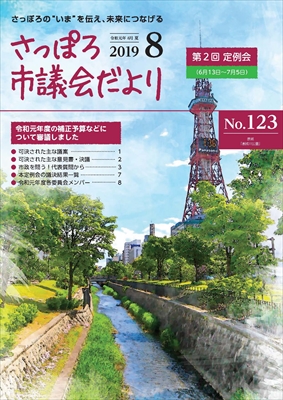
PDF版
| 主な内容 | ページ |
|---|---|
| No.123(令和元年8月夏号) | 全ページ(PDF:3,111KB) |
| 可決された主な議案 | 1ページ(PDF:243KB) |
| 可決された主な意見書・決議 | 2ページ(PDF:355KB) |
| 市政を問う!代表質問から | 3~6ページ(PDF:1,773KB) |
| 本定例会の議決結果一覧、令和元年度各委員会メンバー、永年勤続議員への表彰状を伝達、松浦忠議員を除名 | 7~8ページ(PDF:545KB) |
| 令和元年第3回定例会審議日程、議長・副議長就任のごあいさつ、アメリカ・ポートランド市を訪問しました | 9ページ(PDF:484KB) |
HTML版
令和元年(2019年)8月発行
編集/発行:札幌市議会事務局
電話番号:011-211-3164
FAX:011-218-5143
【目次】
第2回定例会(6月13日~7月5日)令和元年度の補正予算などについて審議しました
令和元年第2回定例会では、令和元年度補正予算や札幌市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例案などの議案17件、諮問1件、意見書4件、決議1件が全会一致または賛成多数で可決されました。
可決された主な議案~補正予算案と条例案~
令和元年度の補正予算案
未来の未来の札幌として描く「誰もが安心して暮らし生涯現役として輝き続ける街」と「世界都市としての魅力と活力を創造し続ける街」を実現するため、「6つのまちづくり」を重点政策として設定し、補正予算を計上しました。一般会計の補正額は34億円で、補正後の予算額は対前年度比1.1%増の1兆227億円となり、当初予算としては過去最大規模となりました。特別会計・企業会計を加えた全会計では、対前年度比1.1%増の1兆6,518億円です。
重点的に取り組む6つのまちづくり
- 安心して暮らせる強く優しい街
- 人材を育み成長を続ける躍動の街
- 女性がさらに輝き活躍する街
- すべての子どもたちが健やかに育つ街
- 魅力と活力にあふれる成熟した街
- 行政サービスを高度化し不断の改革に挑戦する街
| 令和元年度 (百万円) |
令和元年度のうち、これまでの予算 |
令和元年度のうち、今回の補正予算 |
平成30年度 (百万円) |
比較増減 (百万円) |
増減率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 |
1,022,701 |
1,019,342 |
3,359 |
1,011,600 |
11,101 |
1.1 |
| 特別会計 |
363,564 |
363,564 |
0 |
361,675 |
1,889 |
0.5 |
| 企業会計 |
265,517 |
265,289 |
228 |
261,133 |
4,384 |
1.7 |
| 総計 |
1,651,782 |
1,648,195 |
3,587 |
1,634,408 |
17,374 |
1.1 |
条例案
札幌市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例案
子ども医療費助成制度について、新たに小学3年生から6年生までの通院を段階的に助成対象に加えるとともに、入院の一部について助成内容を拡充し、これらに係る自己負担額を初診時一部負担のみとするものです。
札幌市税条例等の一部を改正する条例案
地方税法などの一部改正に伴い、個人市民税について、いわゆる住宅ローン控除を拡充するとともに、子どもの貧困対策に係る非課税措置を新設するほか、軽自動車税について、環境性能割の税率を臨時的に軽減するなどのものです。
可決された主な意見書・決議(概要)
意見書
意見書とは、市政の発展に必要な事柄の実現を要請するため、市議会の意思を決定し、国会や政府に提出するものです。
2019年度北海道最低賃金改正等に関する意見書
政府に対し、2019年度の北海道最低賃金の改正に当たって、下記の措置を講ずるよう強く要望するものです。
- 経済の自律的成長の実現に向け、「2020年までに全国平均1,000円を目指す」という目標を掲げた「雇用戦略対話」における合意を十分尊重し、最低賃金を引き上げること。
- 厚生労働省のキャリアアップ助成金などの各種助成金を有効活用した最低賃金の引き上げを図るとともに、中小企業に対する支援の充実と安定した経営を可能とする実効性のある対策を行うこと。
決議
決議とは、市議会としての意思を決定し、それを対外的に表明するものです。
米国の臨界前核実験に抗議する決議
核兵器の廃絶は、最初の被爆国である日本をはじめ、今や全世界の人類共通の願いとなっています。しかしながら、このたび、米国政府がネバダ州にある核実験場において、2019年2月に臨界前核実験を実施していたとの報がありました。平和都市宣言を行った札幌市において、本市議会は、これまでも核保有国が核性能実験、臨界前核実験および地下核実験を実施した際に抗議の決議を行ってきました。また、米国政府に対しても、再三にわたって核性能実験や臨界前核実験の停止を求めてきましたが、今回、再び臨界前核実験を強行したことは、極めて遺憾です。このように核実験を繰り返すことは、「核兵器のない世界」を目指す国際情勢の流れに逆行し、核兵器廃絶と恒久平和を願う世界の人々の期待を裏切るものです。よって、本市議会は、米国政府に対し、臨界前核実験の強行にあらためて抗議するとともに、核兵器廃絶と核実験中止を求める国際世論を真摯(しんし)に受け止め、今後、いかなる核実験も恒久的に行わないよう強く求めるものです。
⇒意見書および決議の全文は、意見書・決議のページに掲載しています。
市政を問う!~代表質問から~
5人の議員が、市政について市長などに質問しました。
自由民主党:北村光一郎議員
長期の財政見通し
【Q】今後、本市の社会インフラが一斉に更新時期を迎えることや、2030年の冬季オリンピック・パラリンピック招致を目指すことなどを考えると、これまでの中期財政フレームに加え、長期の財政見通しを踏まえたうえで市全体の行政運営を行う必要があると考えます。また、インフラを含む公共施設の更新需要について、数十年先の将来推計を的確に財政運営に反映し、同時に市民の理解も深めていくべきだと考えますが、いかがですか。
【A】今後の公共施設の更新需要やオリンピック・パラリンピック招致に対応したまちづくりを進めていくためには、10~15年先の財政を見通したうえで、4年間の中期財政フレームを示したいと考えています。併せて、50年先の人口減少を踏まえた公共施設の維持更新に係る将来推計と、それに基づく10年間の事業費や施設の床面積の中長期的な将来推計と数値目標についても示し、市民と情報共有を図りながら、財政運営について検討していきます。
まちづくりと教育
【Q】本市に移り住み、生活する人々を増やしていくためには、学校教育の充実は大変重要な要素だと考えます。将来の社会を担う子どもたちに求められる学力を義務教育段階でしっかりと育み、その先の高等教育へつながる教育環境を整えることは、市の魅力を向上させ、企業誘致や移住促進などを通じた本市の発展につながると考えます。本市の子どもたちに育もうとしている学力についての認識と、教育環境が市の内外の子育て世代に与え得る影響をどのように考えていますか。
【A】子どもたちが夢や目標を持ち、その実現に向け、自ら未来を切り開いていくために必要な学力を育むことが重要であると認識しています。子育て世代にとっては、安心して子どもを育てられることが何よりも重要であり、教育環境が与える影響は大変大きいことから、今後も教育環境の充実を図り、子育て世代を含めた誰もが安心して暮らしていけるまちとなるよう取り組んでいきます。
札幌ドーム
【Q】本市では、ファイターズ移転後の札幌ドームでの新たな収入の確保策を検討していますが、移転後は減収および経常収支の赤字が見込まれると聞いております。市民に根付いたプロ野球観戦の文化を継承していくことが重要かつ、多くの市民の声であるため、2030年シーズン以降も札幌ドームでプロ野球開催が実現できるよう、本市が先頭に立って行動するとともに、減収や赤字の解消などの収支見通しを明確に示すべきだと考えますが、いかがですか。
【A】札幌ドームが誕生して以来、プロ野球観戦が市民のごく普通のライフスタイルとなっています。引き続き札幌ドームで試合が見たいという市民やファンの願いをかなえるためにも、札幌ドームで年間数試合のプロ野球開催ができるよう、ファイターズに要望していきます。また、今後の動向も踏まえて経費削減と代替収入策を検討し、収支見通しを立てる際には、新たな市民負担の増加がないよう最大限の努力をしていきます。
第2児童相談所の役割と機能
【Q】児童相談所への児童虐待の相談件数や措置件数は年々増加しており、本市では、第2の児童相談所開設に向け計画を進めています。しかし、単に職員数を増やすだけでは質が低下する懸念があり、職員の専門性を確保・向上することと併せ、二つの児童相談所が、迅速かつ的確に虐待対応・支援を行う体制を確立しなければなりません。二つの児童相談所の役割をどう位置付け、どのような機能を発揮させることによって、児童虐待防止に結びつけていきますか。
【A】新たな児童相談所には、相談支援部門と一時保護部門を一体的に設置することとし、二つの児童相談所それぞれが、所管する地域における専門的な相談支援拠点としての役割を担うことを考えています。相談者にとって、より身近な相談機関を目指すとともに、関係機関がこれまで以上に緊密に連携して支援する機能を高め、虐待の発生予防や早期支援につなげていきます。
民主市民連合:大嶋薫議員
冬季オリンピック・パラリンピック招致
【Q】市長は公約で冬季オリンピック・パラリンピック招致を掲げていますが、現時点では、招致の賛否はほぼ拮抗していると聞いています。大会の実現には、招致機運の盛り上がりや市民からの支持が不可欠であるため、大会を契機に変わっていくまちの姿を「市民と一緒につくりあげる」「イメージを共有する」という姿勢で示し、実践することが必要だと考えます。「市民とともに」という観点から、招致に向けてどのように取り組んでいきますか。
【A】市民の皆さんとともに招致を実現していくためには、招致の意義、開催経費の見込みなどの基本的事項を共有し、相互理解を深めていくことが重要です。新たな計画案については、広く市民に周知したうえで市民と対話する機会を設け、そこで得られた市民の声を計画案に反映させながら、その後も対話を継続して計画案を磨き上げていきます。このような取り組みにより、共感の輪を広げながら、市民と一体となった招致活動を進めていきます。
外国人市民との共生
【Q】本市に住む外国人の数はかなりのペースで増加しており、今後さらに加速していくものと予想されます。一方、外国人が日常生活を営むうえで直面する問題は多方面にわたり、専門機関や民間団体との連携は欠かせません。外国人を単なる労働者としてではなく外国人市民として受け入れることは、多文化共生社会を目指す本市の未来につながるものと考えますが、支援の在り方についてどのように考えていますか。
【A】外国人が抱える多様な問題に総合的に対処できるよう、関係機関や外国人を支える市民のグループだけではなく、地域や企業などの受け入れ機関とも連携することが重要だと認識しています。本市では今後、多言語で対応する総合相談窓口の整備や地域における異文化理解を推進し、全ての外国人を孤立させることなく、ともに生活していく共生社会を目指していきます。
加害者への対応を含むDV対策
【Q】DV被害者の大多数は、さまざまな事情により離婚を選択できず、離婚できた場合も子どもとの面会交流が認められ加害者との接触が続くなど、不安を抱いた生活を強いられています。また、加害者の中には、離婚後に違うパートナーとの間でDVを繰り返し、新たな被害者を生むこともあります。被害者を支援し、DVの根絶を目指すためには、加害者対策に早期に取り組んでいく必要があると考えますが、本市の認識と今後の取り組みについて教えてください。
【A】DV対策において最優先すべき事柄は、被害者の安全・安心の確保です。加害者対策はそれらを高め、DVの再発防止につながる支援の一つとなり得ると認識しています。本市では、若年層に向けたデートDV防止講座など、予防啓発活動を実施しており、今後もこれを継続していきます。また、相談員研修に加害者心理の視点も取り入れるなど、新たな取り組みも進めていきます。
温暖化対策推進計画の改定について
【Q】脱炭素化に向けた環境やエネルギーに関するさまざまな技術は、今後、われわれの生活を大きく変革させ、市民や企業にプラスの経済効果を与えることが期待されています。本市が持続可能なまちづくりを目指すにあたって、これらの技術に関する政策は本市のさまざまな課題解決の糸口になり得るものと考えますが、本市の温暖化対策推進計画の改定作業は、脱炭素化社会の構築に向け、どのような考えのもとに進めていきますか。
【A】今後の温暖化対策においては、将来的な脱炭素社会の実現を見据え、温室効果ガス排出量のさらなる削減が必要と認識しており、また、関連する産業の振興や、エネルギーの自立による防災力の強化など、経済、社会、生活といった他の分野の効果も同時に実現していく視点も重要です。計画の改定にあたっては、こうした視点を持ちながら、幅広くかつ効果的な施策を検討していきます。
公明党:福田浩太郎議員
雪氷エネルギー活用の検討
【Q】本市では、年々増加する除雪費が予算を圧迫するとともに、雪堆積場の郊外化の進行や除雪従事者確保の困難化など、持続可能な除雪体制の維持が大きな課題となっています。一方、石狩市では、雪氷エネルギーの活用による企業誘致に成功しており、これまでお金をかけて処理していた雪を雪氷エネルギーという価値の高いものへ生まれ変わらせています。本市においても、雪氷エネルギーの活用に向けて、関係部局が連携し検討すべきと考えますが、いかがですか。
【A】雪氷エネルギーの活用はさまざまな利用事例があり、本市においてもモエレ沼公園や円山動物園などで導入しています。一方で、施設の整備費や雪の輸送費など、費用対効果の課題もあるため、他都市の取り組み状況や技術進歩などの動向を踏まえながら、今後の可能性について、部局横断的に検討を進めていきます。
地域交通ネットワークの充実
【Q】帰宅時間が遅くなるとバスの便がない、そもそもバスの便数が少ないなど、路線バスの利便性には地域間で大きな差があります。こうした中、企業や地域においては、買い物客に対する無料送迎バスの運行など、さまざまな取り組みが行われています。本市においても、バスネットワークの確保に向けて積極的に取り組んでいくべきだと考えますが、いかがですか。
【A】路線バスについては、路線廃止などにより市民生活に大きな影響が出ることのないよう、赤字路線に対する補助などを実施し、路線の維持に努めているところです。また、乗務員不足などの課題に対応するため、事前予約により運行するデマンドバスの導入などを検討していく考えであり、今後もバス事業者と連携を図りながら、バスネットワークの維持に努めていきます。
SDGs(エスディージーズ)を踏まえた教育の推進
【Q】国連が定める「持続可能な開発目標(SDGs)」の実現を目指すためには、市民自身がその重要性を理解し、実践していくことが肝要であり、SDGsを踏まえた教育を推進する必要があると考えますが、本市はどのように認識し、推進していきますか。
【A】これからの社会を担う子どもたちが、SDGsの理念を学ぶことは重要と認識しています。このため、本年度改定した札幌市教育振興基本計画において、その理念を踏まえた施策を推進するとともに、学校教育の重点にも位置付けています。一人一人の子どもに対し、SDGsが提起するさまざまな課題を身近な問題との関わりから捉え、主体的に行動を起こそうとする意欲や態度を育んでいきます。
日本共産党:吉岡弘子議員
子どもの医療費無償化について
【Q】今回の補正予算案では子ども医療費の助成対象を段階的に小学6年生まで拡大するとしており、大変喜ばれておりますが、市民からは中学校卒業まで拡充してほしいと13,000筆の署名が寄せられています。全国では既に中学校3年生以上に通院助成を行っている自治体が多く、本市は非常に遅れていると考えますが、いかがですか。
【A】本来、住む地域によって子ども医療費の助成水準に差異があることは好ましくないと認識しており、これまでも国に対し、全国一律での取り扱いがされるよう要望してきましたが、引き続き国による新たな医療費助成制度の創設を強く求めていきます。本市の医療費助成については、対象年齢のさらなる拡大を求める声も多く、重要課題だと認識していますが、まずは公約に掲げた小学6年生までの拡大にしっかり取り組んでいきます。
里塚地区に隣接している地域の地盤改良
【Q】札幌市大規模盛土造成地マップによると、市内95カ所の大規模盛土造成地のうち29カ所が清田区となっています。北海道胆振東部地震において、清田区の被害が飛び抜けて多かったことを考えると、地震被害と盛り土の関係性は否定できません。里塚霊園では、川だった場所に盛り土がされており、霊園および霊園の隣接地の宅地においても、既に復旧工事に着手している里塚地区同様、公費による霊園と宅地の一体的な地盤改良が喫緊(きっきん)の課題だと考えますが、いかがですか。
【A】里塚以外の地区では、流動化が生じている状況にはないことから、一体的な地盤改良は想定していません。現在、里塚霊園の隣接地においては、被災メカニズムの把握などの技術的検討を進めており、検討状況などを地域の方に情報提供していきます。
市民ネットワーク北海道:石川さわ子議員
区におけるまちづくりについて
【Q】現在の区のまちづくり推進事業において、各区の特色を生かしたさまざまな事業が行われていますが、区という総合的な市民の生活空間に着目し、地域の課題や要望を政策化して予算立てする仕組みが整っていないと感じます。地域の課題や要望に応じて予算の使い道を決めることができるようにするなど、地域を応援する具体的な取り組みを行うべきですが、今後の区におけるまちづくりをどのように考えていますか。
【A】各区の課題や実情を踏まえたまちづくりの推進は重要であり、これまでも地域の意見などを反映した取り組みを進めてきました。次期アクションプランでは、本庁の部局と全区が連携して実施すべき事業や、区の特色を生かした意欲的な事業について、既存事業とは別に計画化を検討しています。今後も、地域コミュニティーがより活性化していくよう、区の特長を生かしたまちづくりを進めていきます。
本定例会の議決結果一覧
本会議の結果【令和元年第2回定例会・審議結果】のページをご覧ください。
令和元年度各委員会メンバー
常任委員会
|
総務委員会 |
財政市民委員会 | 文教委員会 |
|---|---|---|
| 企画、都市計画、清掃、環境保全、消防など | 住民活動、市民生活、区役所、文化、財政など | 学校教育、社会教育、子育て支援など |
|
(委員長)小竹 ともこ (副委員長)成田 祐樹 武市 憲一 山田 一仁 飯島 弘之 小田 昌博 桑原 透 山口 かずさ 田島 央一 國安 政典 小口 智久 池田 由美 |
(委員長)中村 たけし (副委員長)田中 啓介 高橋 克朋 細川 正人 北村 光一郎 村松 叶啓 ふじわら 広昭 うるしはら 直子 福田 浩太郎 佐藤 綾 石川 さわ子
|
(委員長)松井 隆文 (副委員長)前川 隆史 三上 洋右 よこやま 峰子 小須田 ともひろ 小野 正美 松原 淳二 たけのうち有美 森山 由美子 村上 ひとし 長屋 いずみ
|
| 厚生委員会 | 建設委員会 | 経済観光委員会 |
| 社会福祉、国民健康保険、保健衛生など | 道路、公園、河川、除雪、住宅、上下水道、区画整理など | 産業、観光、スポーツ、市立病院、市営交通など |
|
(委員長)太田 秀子 (副委員長)三神 英彦 勝木 勇人 こじま ゆみ 村山 拓司 しのだ 江里子 岩崎 道郎 恩村 健太郎 丸山 秀樹 くまがい 誠一 佐々木 明美 |
(委員長)中川 賢一 (副委員長)かんの 太一 こんどう 和雄 佐々木 みつこ 伴 良隆 阿部 ひであき 大嶋 薫 林 清治 水上 美華 竹内 孝代 吉岡 弘子 |
(委員長)好井 七海 (副委員長)藤田 稔人 鈴木 健雄 長内 直也 川田 ただひさ 峯廻 紀昌 村上 ゆうこ あおい ひろみ わたなべ 泰行 小形 香織 千葉 なおこ |
議会運営委員会
| 議会運営委員会 |
|---|
| 議会運営上必要な事項に関すること |
|
(委員長)飯島 弘之 (副委員長)しのだ 江里子 北村 光一郎 小竹 ともこ 川田 ただひさ 林 清治 中村 たけし 福田 浩太郎 丸山 秀樹 小形 香織 太田 秀子 |
永年勤続議員への表彰状を伝達
7月5日、本会議場において、永年勤続議員に係る表彰状の伝達式が行われました。これは、6月11日に東京都で開催された全国市議会議長会定期総会において、札幌市の議員が在職20年以上の表彰を受けたことによるものです。表彰された議員は以下のとおりです。
- 在職20年以上:五十嵐徳美議員、長内直也議員、恩村一郎前議員、こんどう和雄議員、坂本きょう子前議員、山田一仁議員
松浦忠議員を除名
松浦忠議員は、5月13日の本会議において、地方自治法の規定に基づき臨時議長に就任しましたが、その際、他の議員の発言を認めないなど議事を進行する立場の者としての責務を果たさず、長時間議事が滞りました。このことにより、議会活動に支障を与えるとともに、市民生活に多大な影響を及ぼす危険性があったとして、11人の議員から懲罰を求める動議が提出され、懲罰特別委員会が設置されました。同委員会での審査の結果、賛成多数で除名の懲罰を科すべきものと決定されました。その後、6月21日の本会議で出席議員の4分の3以上の賛成により、地方自治法第134条第1項の規定に基づき松浦議員に除名の懲罰を科すことが可決されました。
令和元年第3回定例会審議日程
本会議の結果【令和元年第3回定例会・日程表】のページをご覧ください。
議長・副議長就任のごあいさつ
- 第34代議長:五十嵐徳美(東区選出6期)
- 第40代副議長:桑原透(清田区選出5期)
このたび、札幌市議会議長、副議長に就任しましたので、ごあいさつを申し上げます。3年後の2022年に市制施行100周年を迎える札幌市は、今後、超高齢化に加えて人口減少社会が到来するとともに、社会基盤の更新や災害に強いまちづくり、子育て・女性活躍支援など、さまざまな課題への取り組みが求められます。二元代表制の一翼を担う市議会は、市民が住んで良かったと実感でき、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めていくため、皆さまの声に耳を傾け、一層活発な議会活動を展開していきます。
アメリカ・ポートランド市を訪問しました
札幌市とポートランド市の姉妹都市提携60周年を迎え、桑原副議長を団長に議員団9名がポートランド市を訪問しました。このたびの記念訪問には、議員団のほか、秋元市長、市民訪問団、経済訪問団、大学関係者など、総勢約80名が参加しました。訪問中は、ポートランド市主催の記念式典やレセプションに出席し、ポートランド市民らとの親交を深めたほか、テッド・ウィラー・ポートランド市長および寺岡敬・在ポートランド総領事を表敬訪問し、現地情勢についてお話を伺い、意見交換を行いました。今回の訪問を通して、さまざまな場面で大変温かく迎えられ、この60年間で築き上げてきた両市の友好関係の深さを、改めて実感する貴重な機会となりました。今後も両都市間の交流を深め、相互発展に取り組んでいきます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.