ここから本文です。
さっぽろ市議会だよりNo.139
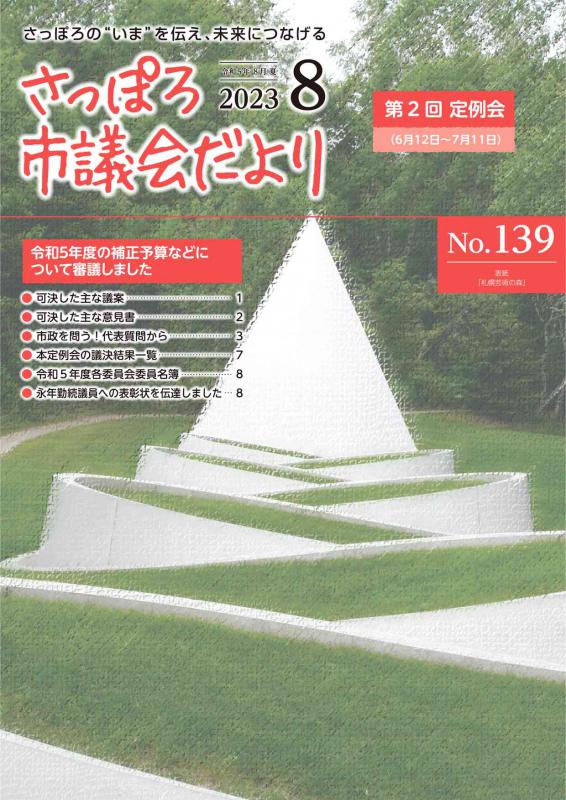
PDF版
| 主な内容 | ページ |
|---|---|
| No.139(令和5年8月夏号) | 全ページ(PDF:2,421KB) |
| 可決した主な議案 | 1ページ(PDF:488KB) |
| 可決した主な意見書 | 2ページ(PDF:488KB) |
| 市政を問う!代表質問から | 3~6ページ(PDF:915KB) |
|
本定例会の議決結果一覧 令和5年度各委員会委員名簿 永年勤続議員への表彰状を伝達しました |
7~8ページ(PDF:397KB) |
|
議長・副議長就任のごあいさつ 議会事務局からのお知らせ |
9ページ(PDF:1,298KB) |
音声版さっぽろ市議会だより
音声版さっぽろ市議会だよりNo.139(YouTubeに移動します。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.