ここから本文です。
さっぽろ市議会だよりNo.122
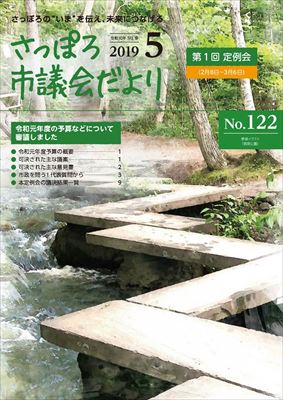
PDF版
| 主な内容 | ページ |
|---|---|
| No.122(令和元年5月春号) | 全ページ(PDF:2,559KB) |
| 令和元年度予算の概要、可決された主な議案・意見書 | 1~2ページ(PDF:378KB) |
| 市政を問う!代表質問から | 3~8ページ(PDF:1,414KB) |
| 本定例会の議決結果一覧 | 9~10ページ(PDF:202KB) |
| 議会事務局からのお知らせ | 11ページ(PDF:837KB) |
HTML版
令和元年(2019年)5月発行
編集/発行:札幌市議会事務局
電話番号:011-211-3164
FAX:011-218-5143
【目次】
第1回定例会(2月8日~3月6日)令和元年度の予算などについて審議しました
平成31年第1回定例会では、令和元年度予算に関わる議案や札幌市児童福祉法施行条例の一部を改正する条例案などの議案66件、意見書5件が全会一致または賛成多数で可決されました。
令和元年度予算の概要
令和元年度の一般会計予算は、統一地方選挙を控えていることから骨格予算として編成しましたが、防災・減災事業や子ども・子育て支援などの喫緊(きっきん)の課題に対応するため、前年度に比べ0.8%増の1兆193億円を計上し、一般会計の予算としては過去最大規模となりました。なお、特別会計・企業会計を加えた全会計では、前年度に比べ0.8%増の1兆6,482億円を計上しています。
予算の主な使い道
- 暮らし・コミュニティ
- 私立保育所などの整備を補助
- 通院・入院の医療費自己負担が原則無料となる対象を小学校2年生までに拡大
- 産業・活力
- プレミアム商品券の発行
- ラグビーワールドカップ2019大会の開催
- 低炭素社会・エネルギー転換
- 次世代エネルギーの普及促進
- 都市空間
- 清田区里塚地区の復旧工事
令和元年度の予算規模
| 区分 | 令和元年度(億円) | 平成30年度(億円) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
|
一般会計 |
10,193 |
10,116 |
0.8 |
|
特別会計 |
3,636 |
3,617 |
0.5 |
|
企業会計 |
2,653 |
2,611 |
1.6 |
|
合計 |
16,482 |
16,344 |
0.8 |
一般会計の歳入内訳
| 区分 | 市税(億円) | 国庫支出金(億円) | 地方交付税(億円) | 市債(億円) | 諸収入(億円) | その他(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
歳入 |
3,309 |
2,364 |
1,083 |
1,027 |
895 |
1,515 |
一般会計の歳出内訳
| 区分 | 保健福祉費(億円) | 職員費(億円) | 土木費(億円) | 公債費(億円) | 経済費(億円) | その他(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
歳出 |
3,963 |
1,577 |
1,058 |
875 |
774 |
1,946 |
可決された主な議案~補正予算案と条例案~
平成30年度の補正予算案
以下の経費など、全会計総額85億7,500万円を増額する補正予算が可決されました。
- 清田区里塚地区の復旧工事に係る経費
- 学校改築費などの防災・減災関連経費
- 老朽化した公園施設の改修費
- 除雪費
条例案
札幌市児童福祉法施行条例の一部を改正する条例案
児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、児童指導員の資格要件に幼稚園教諭の免許状を有する者を追加するものです。
可決された主な意見書
意見書
意見書とは、市政の発展に必要な事柄の実現を要請するため、市議会の意思を決定し、国会や政府に提出するものです。
統計不正問題の原因究明と早期解決を求める意見書
本年1月、国の56の基幹統計のうち、約4割の統計に誤りや手続きなどの問題があったことが判明しました。特に、毎月勤労統計では、全数調査とするとしていたところを一部抽出調査とするなど、2004年から15年間もの長期にわたり不正が行われました。その結果、雇用保険や労災保険などが過少支給となり追加給付が必要な人は、延べ約2,000万人にも上り、順次、追加給付を行うこととなりました。また、事実関係を調査するために厚生労働省が設置した第三者委員会は、1月22日に報告書を公表しましたが、後に、同委員会によるヒアリングは、同省の審議官や大臣官房長が同席していたことや、大半が同省職員により行われていたことが判明し、同委員会の中立性に疑義が生じました。毎月勤労統計は、景気判断や、都道府県の各種政策決定の指針とされるほか、雇用保険などの給付額改定、民間企業などにおける給与改正や人件費算定、人事院勧告の資料とされるなど、国民生活に深くかかわる重要な統計です。よって、政府に対し、この問題について原因究明し、早急に再発防止策を講ずるとともに、雇用保険などの必要な追加支給を早期に行うよう強く要望するものです。
柔軟仕上げ剤等の家庭用品に含まれる香料による健康被害の実態解明を求める意見書
近年、家庭で使用する柔軟仕上げ剤や消臭剤などに含まれる香料によって、頭痛や吐き気などの健康被害を訴える人が増加しています。また、特定非営利活動法人日本消費者連盟が、2017年に2日間開設した相談窓口「香害110番」には、柔軟仕上げ剤などの香りについて、213件もの相談が寄せられました。こうした中、日本石鹸洗剤工業会は、2018年7月、「衣料用柔軟仕上げ剤の品質表示自主基準」を改定し、香りに関する注意喚起として、柔軟仕上げ剤の容器などに周囲への配慮と適正使用量を守る旨を表示することとしましたが、この問題の根幹は、香料が与える健康被害の実態解明が進んでいないことや、自ら使用する柔軟仕上げ剤の香料が他人に苦痛を与えている場合もあることについての理解が社会全体として進んでいないことにあります。よって、政府に対し、消費者の健康で安心な暮らしに資するよう、香料の成分の安全性や香料による健康被害の実態を徹底して検証した上で、実効性のある施策を実施するよう強く要望するものです。
⇒可決された意見書の全文は、意見書・決議のページに掲載しています。
市政を問う!~代表質問から~
8人の議員が、市政について市長などに質問しました。
自由民主党:宮村素子議員
新年度における復旧支援策
【Q】本市では、北海道胆振東部地震による被災者に対し、宅地復旧支援事業や被災家屋の公費撤去事業などを行っていますが、公費撤去事業は国の平成30年度の補助金を主要財源としていることなどから、本年度末が申請期限となっています。しかし、冬期間は積雪や凍結のため調査や復旧工事などの実施が難しく、積雪や融雪に伴う被害の拡大・進行も予想されます。そのため、4月以降に工事して支援・補助を受けたいと考えている被災者が多数想定されますが、これらの支援・補助事業について、新年度ではどのように取り組んでいきますか。
【A】冬期間の被害状況や復旧工事の実情を踏まえ、本市独自の支援策である宅地復旧支援事業などについては、新年度も引き続き実施します。また、国の制度に基づく各種の対策についても、引き続き実施できるよう国などに求めており、このうち、公費撤去については、申請期間を平成31年6月末まで延長する方向で協議中です。
新年度予算の建設事業費
【Q】本市の平成31年度予算案は、「災害からの復旧・復興、防災・減災」を柱の一つに据えて関連予算を計上していますが、一方で、本年10月からの消費税率引き上げによる地域経済への影響にも配慮する必要があります。そこで、投資の誘発につながる再開発事業に関する建設事業費を積極的に計上し、十分な予算規模を確保するなど、経済活性化に向けた取り組みを強化すべきだと考えますが、いかがですか。
【A】平成31年度予算の建設事業費は、中期計画であるアクションプランに掲げた事業を着実に計上しつつ、被災地区の面的な復旧工事を始め、「災害からの復旧・復興、防災・減災」関連に重点的に予算を配分しました。また、民間投資の誘発につながる再開発事業など、経済活性化に資する事業も積極的に計上し、加えて、公共事業は現時点で必要と見込まれる事業費の全額を計上しました。災害に強いまちづくりと経済の活性化を進めつつ、インフラを含む公共施設の的確な維持・更新にもしっかりと対応した予算としており、誰もが安心して暮らせるまちづくりに向け、必要な予算規模を確保したと認識しています。
母子保健施策の今後の進め方
【Q】近年、児童虐待が増加していますが、背景には、親自身が子どもの頃に十分な愛情を受けて育てられなかったために育て方が分からない、といった世代間の負の連鎖があり、いわゆる愛着関係を十分に築けない状況が増えているのではないかと懸念しています。母親に手を差し伸べ母子の愛着形成を促すことで、児童虐待を未然に防ぎ、子どもの人権と健康を守ることができると考えますが、今後の母子保健施策をどのように進めていきますか。
【A】母子保健施策には、母子の心身の健康保持のみならず、母親の育児不安に対する支援や児童虐待予防の取り組みが求められています。今後は、母親一人一人の気持ちに寄り添いながら、きめ細やかな支援を行うことが重要であることから、支援が必要な母親などの早期把握、医療機関とのネットワーク体制の拡充など、妊娠期からの包括的な支援体制の充実を図り、児童虐待予防に取り組んでいきます。
清田区の当面の交通課題への対策
【Q】清田区は、軌道系交通機関が整備されておらず、バスを中心に公共交通のネットワークが形成されていますが、バスには定時性などの課題があり、利便性の確保に取り組む必要があります。また、近年の大型商業施設の立地などにより、主要な幹線道路で渋滞が発生しており、その解消が喫緊(きっきん)の課題となっています。地下鉄の延伸の実現に向けては時間を要することも想定される中、当面の交通課題に対し、しっかりとした対策を早急に講じていく必要があると考えますが、いかがですか。
【A】バスの利便性確保については、バス事業者と連携しながら、バスの現在地をスマートフォンなどで確認できるバスロケーションシステムを導入するなど、バス待ち環境の改善を進めるとともに、ノンステップバスの導入も推進しています。渋滞の解消については、札幌新道などの延伸のほか、交通の分散化を図るため、ドライバーへの渋滞情報の提供などを行っており、国道36号と厚別東通の交差点改良の検討をはじめ、必要な対策を進めていきます。
民主市民連合:畑瀬幸二議員
市長の政治姿勢
【Q】市長は、就任以来、「誰もが安心して暮らし生涯現役として輝き続ける街」と「世界都市としての魅力と活力を創造し続ける街」の実現に向けて市政運営を進め、成果を挙げてきました。一方、北海道胆振東部地震に見舞われた本市は、災害に強いまちづくりに取り組んでいくことが喫きっきん緊の課題となっているほか、人口減少・超高齢社会の到来を踏まえ、将来を見据えた持続可能なまちづくりが今後一層求められていくと考えます。市長は2期目に挑戦する意向を表明しましたが、公約の達成状況を踏まえた1期目の所感と、2期目を目指す決意を聞かせてください。
【A】市長就任以来、市民の生命と財産、幸せを守るため、この4年間全力で取り組んできました。その結果、子育て支援など、市民と約束した事柄については成果も表れつつあることから、これまでの政策の方向性に間違いはなかったと認識しています。一方、人口減少・超高齢社会に向けた取り組みは道半ばであり、また、地震からの早期復旧・復興に引き続き取り組み、災害に強いまちづくりをより一層進めていかなければなりません。こうした想いを新たに、4年前に描いた本市の未来像の実現に向け、引き続き市政を担いたいと考えています。
防災教育の充実
【Q】阪神・淡路大震災以降、全国の学校で防災教育が浸透しつつあります。多くの人が確かな防災知識を身につけることが真に災害に強いまちづくりにつながることから、このたびの地震を機に、本市でも、幼稚園から小学校、中学校、高等学校までの各段階に応じて、防災教育の充実を図るべきだと考えますが、いかがですか。
【A】本市では、学校や地域の実態に合わせた避難訓練を行うなど、日頃から防災教育に取り組んでいますが、このたびの地震により、幼児期からの発達段階に応じて、災害に備え安全に行動できる子どもを育むことが重要であると改めて認識しました。また、市立高校で取り組んでいる課題探究的な学習において、専門的な知識や技能と防災を関連付けるなど、自ら考え、適切に判断できるようにすることも重要です。今後も、子どもたちが率先して自他の生命を尊重し行動できるようになることはもとより、災害に強いまちづくりに主体的に貢献しようとする意識を育むことができるよう、防災教育を一層推進していきます。
コンセッション方式の導入
【Q】昨年成立した改正水道法により、水道事業の運営権を民間企業へ売却できるコンセッション方式の導入が可能となりました。しかし、本市の水道インフラは計画的な更新が必要であり、また、このたびの迅速な震災対応など、これまで培われ、継承されてきた職員の技術や知識などは一朝一夕に養われるものではありません。今後も本市の責任の下、市民に安心安全な水を供給していくべきだと考えますが、いかがですか。
【A】本市の水道事業は、人口減少による収益の減少や技術の継承などの問題を抱えていることから、業務効率化などによる良好な経営状況の維持や、計画的な研修による技術の継承など、持続可能な水道事業の実現に向けた取り組みを推進しています。水道は市民の生活や健康に直接関わる重要なライフラインであるため、今後も本市が運営を担っていきます。
公立夜間中学の設置
【Q】公立夜間中学の設置については、国から設置の推進がうたわれる一方、予算措置などの具体的な動きはなく、設置に至らない地域が多いのが現状です。そのような中、本市では、通学が想定される方々の多様な教育ニーズを把握するため、個別の聞き取り調査に着手したと聞いています。また、北海道が設置した「夜間中学等に関する協議会」でも、本市に設置すべきとの意見が多かったとのことです。さまざまな理由で学ぶ機会を失った多くの人たちの学ぶ権利を取り戻すため、本市に公立夜間中学を設置すべきだと考えますが、いかがですか。
【A】公立夜間中学は、さまざまな事情により十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方や、近年増加する日本国籍を有しない方などに、教育を受ける機会を保障するため、重要なものと認識しています。昨年、国から設置推進のための具体的な運用基準が示されたことや、このたび、北海道の協議会で市内への設置について一定の意見集約が図られたことから、本市としても前向きに検討していきます。
公明党:涌井国夫議員
さっぽろ連携中枢都市圏
【Q】本市は、少子高齢化や人口減少を踏まえ、一定の人口規模を有した活力ある社会経済の維持を目的に連携中枢都市圏の形成を目指していますが、圏域の形成により、どのような視点が求められると考えていますか。また、「さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン(案)」では、5年間という期限を定め、さまざまな連携事業を実施することとされていますが、長期にわたって連携していく中で、今後5年間の取り組みをどう位置付けていますか。
【A】連携中枢都市圏の中心となる本市は、市域を超えた圏域全体の発展に資する取り組みを積極的に担っていき、連携市町村の魅力・活力の向上が本市にも好影響を及ぼすことを十分に意識しながら、連携市町村と本市の発展の調和を図っていく視点が重要と考えています。また、今後5年間は将来に向けた基礎固めの期間と考えており、経済分野での成果の積み重ねや、観光分野などの事業の具体化を図っていくことなどを想定しています。
社会包摂(ほうせつ)の観点での文化芸術振興
【Q】本市では、議員提案による「札幌市文化芸術振興条例」などに基づき、文化芸術の振興を進めてきました。一方、国は、昨年3月策定の「文化芸術推進基本計画」などにより、文化芸術の社会包摂(※)機能を生かした「心豊かで多様性のある社会」などを、今後の目指すべき姿として掲げています。年齢、障がいの有無などに関わらず、あらゆる人が文化芸術に触れ、参加できる機会をつくることは、多様な価値観の尊重や、まちのにぎわい創出、さらには文化芸術を地域の産業として育むことにもつながるものと考えますが、今後の文化芸術振興について、どのように考えていますか。
(※)社会包摂:社会的に弱い立場にある人々をも含め市民ひとりひとり、排除や摩擦、孤独や孤立から援護し、社会の一員として取り込み、支え合う考え方のこと。
【A】文化芸術の振興は、本市が掲げる「互いに手を携え、心豊かにつながる共生のまち」の実現に向けて大きな役割を担うものであり、その具体的な取り組みとして、身体の不自由な方も楽しめるジャズイベントや親子で参加できるアート企画などを実施しています。今後も、障がいの有無、年齢、国籍などに関わらず、全ての方にとって、文化芸術に触れる機会がより身近なものとして感じられるよう、取り組んでいきます。
サンピアザ水族館のリニューアル
【Q】本市の観光の魅力は食と自然に依存する傾向が強く、滞在型観光を促す「楽しめるスポットや体験」が少ないことが弱みですが、本市唯一の総合都市型水族館であるサンピアザ水族館は、滞在型観光を促す観光資源となり得ると考えます。そこで、水族館が立地する新さっぽろ地区で進行中の再開発事業に合わせて、水族館の将来的なリニューアルを検討するべきだと考えますが、いかがですか。
【A】サンピアザ水族館は、科学・社会文化の振興発展に寄与する施設として昭和57年に新さっぽろ地区に設置され、子どもの教育施設としても親しまれています。今後は、現在進んでいる再開発事業を見据えて相乗効果が得られるよう、設備の更新などを含め、効果的な運用について運営会社と検討していきます。
障がい者雇用の推進
【Q】障がいのある方の雇用の推進は、行政が率先して取り組むべきであり、また、単に採用するだけではなく、採用後もやりがいを持って長く続けられるような支援体制を整えることも重要です。本市は、本年度から知的障がいや精神障がいのある方も採用選考の対象としましたが、その選考結果と採用する職員に対する配慮はどのようになっていますか。また、知的障がいのある方には、試験方法でも配慮が必要であると考えますが、今後の選考について、どのように考えていますか。
【A】本年度の選考結果は、最終合格者7名、内身体障がいのある方が5名、精神障がいのある方が2名となっています。障がいのある方に対しては、採用の前後においてきめ細やかな面談を行い、本人が抱える不安や必要な配慮事項などを把握し、職場環境の改善など、できる限りの対応を行っています。また、今後の採用選考については、本年度の選考結果を検証の上、国や他自治体の取り組みなども参考にしながら検討していきます。
日本共産党:村上ひとし議員
学童保育に従事する職員の配置基準
【Q】平成30年12月、国は学童保育に従事する職員について、おおむね40人以下の児童に対し職員を2人以上配置するという現在の基準を、「従うべき基準」から「参酌(さんしゃく)すべき(参考にすべき)基準」へと緩和することを閣議決定しました。しかし、現在の基準は子どもたちの放課後の健全育成のために必要最低限のものであると考えますが、いかがですか。
【A】学童保育に従事する職員の配置基準については、年齢や発達状況の異なる子どもたちを同時にかつ継続的に育成支援する必要があることなどの理由から設けられたものと認識しています。今回の国の決定は地域の実情などを踏まえた柔軟な対応を可能とするためのものですが、本市としては、この基準を最低基準と位置付け、常にこれを上回るよう努めていることや、利用児童数の実態からも、あえてこれを緩和する必要はないと考えています。
新さっぽろ駅周辺のまちづくり
【Q】北海道日本ハムファイターズが本拠地を北広島市に移転することにより、隣接する厚別区の新さっぽろ駅周辺では、車の渋滞のほか、利用が集中するJRの乗降客の安全性確保などの課題が出てくることが予測されます。野球を観戦する市民の交通利便性と安全性を向上させる上でも、今後の新さっぽろ駅周辺のまちづくりは、JR北海道との連携など、本市が積極的に関与して課題を解決していく責任があると思いますが、いかがですか。
【A】新さっぽろ駅周辺では、地域交流拠点としての多様な機能集積を図るとともに、充実した交通結節機能を生かして、江別市や北広島市などの生活を支える拠点としてのまちづくりを進めています。今後、交通の円滑化などの課題に対しては、市民の利便性や安全・安心を確保する必要があるという認識のもと、JR北海道など関係機関と連携し、状況に応じた施策を講じていきます。
改革:松浦忠議員
町内会に設置した防犯カメラ
【Q】本市は、市内の篤志家からの寄付により防犯カメラ設置補助制度を設け、町内会に防犯カメラを設置していますが、これは憲法13条の肖像権やプライバシー権を侵害するものだと思います。また、本市が作成した補助金申請の手引きには、プライバシーに対する配慮について、具体的な記載がないと思いますが、いかがですか。
【A】肖像権やプライバシー権は、憲法第13条で保障された権利であり、防犯カメラの設置により個人の権利が侵害されてはならないと認識しています。一方、防犯カメラによる撮影が適法か否かについて、判例では、肖像権やプライバシーの制約の程度を個々のケースごとに判断しています。したがって、防犯カメラの設置が、直ちに権利侵害につながるものではありませんが、防犯カメラが個人の権利を侵害することがないよう、町内会に丁寧な説明を行うとともに、手引きについても改めて必要な見直しを行っていきます。
対話集会に参加した市民への対応
【Q】平成31年2月1日に開催された市民と市長の対話集会で、ある市民が、市営住宅の入居契約者が亡くなった場合に同居人はそのまま生活できるのかということについて尋ねましたが、市長は、個別の案件であることを理由に、結論を述べませんでした。市民は、市長の考え方や今後の取り組みなど、市長にいろいろなことを聞きたいと思って集会に参加していると思いますが、いかがですか。
【A】このたびの対話集会は、できるだけ多くの方に質疑や討論をしてもらうという趣旨から、主催者により、質問は簡潔に1問だけとして進められました。そこで、政治姿勢などとは異なり、参加した方の個人的な事情に係る質問については、時間があまりない中、その場で答弁する状況にはないことを説明しました。その後、具体的な問い合わせはありませんが、回答を拒否しているものではありません。
無所属:坂本きょう子議員
国保短期証の窓口留め置き
【Q】本市では、国民健康保険料を滞納している世帯に対して4カ月ごとの短期証を発行していますが、昨年11月の年次更新では、13,393世帯のうち5,453世帯が窓口交付と称して郵送されずに窓口に留め置かれています。これは国民健康保険法施行規則第6条の「市町村は、世帯主に対し、被保険者証を交付しなければならない」という規定に反する行為であり、役所に取りに行くこと自体が大きなプレッシャーとなる方にとっては、受診をためらうことになりかねないと思われるため、直ちにやめるべきです。また、折衝機会を確保するために活用するとしても、まずは留め置き期間の短縮を図るべきだと考えますが、いかがですか。
【A】平成21年12月の厚生労働省通知によると、短期証の交付の趣旨は、滞納世帯との接触の機会を設けることであり、一定期間窓口で留保することも認められています。本市においても、窓口交付は接触機会の確保のため、一定の効果があるものと考えており、今後も、受診抑制につながらないように十分な配慮をした上で継続していきます。また、留め置き期間については、現在北海道が短期証の窓口交付の運用に関して検討中であるため、その動向も見据えて、今後も検討していきます。
市民ネットワーク北海道:石川佐和子議員
障がい当事者を対象としたアンケート
【Q】北海道胆振東部地震は、多くの市民が災害への備えの必要性を認識する機会になりました。中でも障がい当事者は、災害時に必要な情報を得られず孤立してしまう場合もあり、また、自力での避難が難しい重度の障がい当事者にとっては、地域や福祉関係者、行政による避難支援の取り組みが不可欠であることから、障がい当事者の災害時の安心・安全の確保のため、一人一人の障がい特性などを踏まえた避難計画の作成が重要であると考えます。そこで、実効性のある計画を作るために、障がい当事者が今回の災害でどのようなことに困り、どのような支援を必要としたのか、対象を一部に限定せずに、広くアンケートを実施すべきだと考えますが、いかがですか。
【A】本市では、これまで、障がい当事者を取り巻く災害時の課題については、さまざまな機会を通じて障がい当事者や関係者の意見を聞いてきました。今回の災害を踏まえ、市民の安全確保につなげるため、現在、人工呼吸器などを使用する障がい当事者を対象としたアンケートの実施に向けて取り組んでいます。また、平成31年度に予定している障がい者プランの見直しに向けた実態調査にも、今回の災害を踏まえた設問を盛り込むなど、引き続きさまざまな機会を捉えて、幅広く障がい当事者の声の把握に努めていきます。
札幌党:中山真一議員
受動喫煙対策の強化
【Q】平成30年に公布された、受動喫煙対策を強化する改正健康増進法は、個人や中小企業が経営する客席面積100平方メートル以下の既存飲食店に対して設けられた経過措置により、都市部では飲食店の70~80パーセントが喫煙可能になると推計されています。一方、国際オリンピック委員会は、たばこのない五輪推進のため過去に厳しい規制を設けていることから、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催地の東京都や競技会場となる千葉市では、より厳しい規制内容の条例を独自に制定しています。本市は、同じく競技会場となることに加え、冬季オリパラ招致を目指していることから、2020年までに東京都や千葉市と同レベルの条例を制定するなど、より踏み込んだ受動喫煙対策を進めるべきだと考えますが、いかがですか。
【A】本市は、冬季オリパラ招致を目指す都市として、積極的にたばこ対策に取り組んでいかなければならないと認識しており、本年1月1日より、本庁舎や区役所をはじめ多くの施設を全面禁煙としました。2020年4月の改正健康増進法全面施行に向けて、飲食店での受動喫煙対策の推進、禁煙を望む市民への支援、啓発の強化などさまざまな取り組みをしっかりと進めていきます。なお、北海道では受動喫煙防止条例の制定に向けた検討が行われる予定であるため、本市も検討に参画し、密接に連携しながら対策を進めていきます。
本定例会の議決結果一覧
本会議の結果【平成31年第1回定例会・審議結果】のページをご覧ください。
議会事務局からのお知らせ
第24期市議会閉会あいさつ:災害に強いまちづくりを
3月6日、平成31年第1回定例会最終日の本会議が開かれました。山田一仁議長から、「この4年を振り返る上で忘れてはならないのは、北海道胆振東部地震であります。私たちは、住宅の損壊や液状化など、市民生活にかつてない被害をもたらした震災を契機として、さらなるスピード感を持ち、これまでにも増して市民・行政が一丸となり、災害に強いまちづくりを推進していかなければなりません。」と閉会のあいさつがありました。
インターネット中継をご利用ください
本市議会では、本会議、予算・決算特別委員会、調査特別委員会のインターネット中継を実施しています。また、会議終了からおおむね5日後には、録画映像も公開しています。市議会ホームページから、ぜひご利用ください。
電子書籍版さっぽろ市議会だより
電子書籍サイトやスマートフォンアプリで「さっぽろ市議会だより」をご覧いただけます。ぜひご利用ください。
掲載先
- マチイロ
- 札幌市電子図書館
- ホッカイドウイーブックス
- 北海道の広報まるごと検索くん
政務活動費の収支報告書などを閲覧できます
市議会各会派に交付した平成30年度分の政務活動費について、収支報告書と領収書などの写しの閲覧が始まります(どなたでも閲覧できます)。
- 閲覧が可能となる日:6月7日(金曜日)
- 閲覧可能日時:午前8時45分~午後5時15分(土曜、日曜、祝休日を除く)
- 閲覧場所:市役所本庁舎(中央区北1条西2丁目)15階議会図書室
政務活動費とは?
地方自治法第100条第14項から第16項までの規定により制定された「札幌市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、札幌市議会における会派または所属議員が行う調査研究、研修、広報広聴、市民相談、要請陳情、会議への参加など、市政の課題および市民の意思を把握し、市政に反映させる活動ならびに市民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費の一部として、議会における会派に対して、次のとおり交付されるものです。
- 対象:会派(所属議員が1人の場合を含む)
- 金額:月額40万円×各月における当該会派の所属議員数
- 交付方法:4月、7月、10月、1月にそれぞれ3カ月分を交付
※各会派は、毎年度その収入・支出の状況を支出の科目(使途)ごとに報告することになっています。
※年度末において残額があった場合は返還します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.