ここから本文です。
さっぽろ市議会だよりNo.118
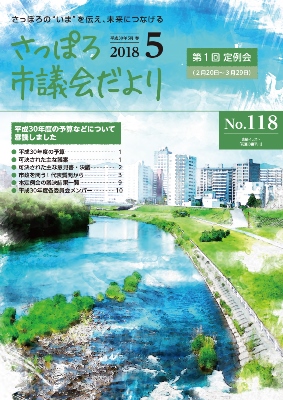
PDF版
| 主な内容 | ページ |
|---|---|
| No.118(平成30年5月春号) | 全ページ(PDF:8,888KB) |
| 平成30年度の予算、可決された主な議案・意見書・決議 | 1~2ページ(PDF:401KB) |
| 市政を問う!代表質問から | 3~8ページ(PDF:1,105KB) |
| 議決結果一覧、平成30年度各委員会メンバー | 9~10ページ(PDF:231KB) |
| 議員逝去、平成30年第2回定例会審議日程、政務活動費の収支報告書などを公開 | 11ページ(PDF:499KB) |
HTML版
平成30年(2018年)5月発行
編集/発行:札幌市議会事務局
電話番号:011-211-3164
FAX:011-218-5143
【目次】
第1回定例会(2月20日~3月29日)平成30年度の予算について審議しました
平成30年第1回定例会では、平成30年度予算や札幌市手話言語条例案などの議案60件、陳情1件、意見書8件、決議1件が全会一致または賛成多数で可決されました。
平成30年度の予算
~本定例会で可決した今年度の予算概要~
平成30年度の一般会計予算額は、待機児童解消などの重点政策の影響などにより前年度に比べ1.5%増の1兆116億円を計上し、当初予算ベースでは市政史上初めて1兆円の大台を突破しました。なお、特別会計・企業会計を加えた全会計では、前年度に比べ1.1%減の1兆6,344億円を計上しています。
| 区分 | 30年度(億円) | 29年度(億円) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
|
一般会計 |
10,116 |
9,965 |
1.5 |
|
特別会計 |
3,617 |
3,977 |
-9.1 |
|
企業会計 |
2,611 |
2,590 |
0.8 |
|
合計 |
16,344 |
16,532 |
-1.1 |
| 区分 | 市税(億円) | 国庫支出金(億円) | 市債(億円) | 諸収入(億円) | 地方交付税(億円) | その他(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
歳入 |
3,222 |
2,241 |
1,137 |
982 |
1,005 |
1,529 |
| 区分 | 保健福祉費(億円) | 職員費(億円) | 土木費(億円) | 経済費(億円) | 公債費(億円) | その他(億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
歳出 |
3,813 |
1,572 |
1,033 |
823 |
866 |
2,009 |
予算の主な使い道
| 暮らし・コミュニティ |
|
| 産業・活力 |
|
| 低炭素社会・エネルギー転換 |
|
| 都市空間 |
|
可決された主な議案~前年度の補正予算案と主な条例案~
平成29年度の補正予算案
以下の経費などを追加するものです。
- 教育環境を向上するための学校施設の整備費
- 市営住宅の改修や建設工事費
- 市立札幌病院の経営を支援するための運転資金の貸し付け
- 生活保護費
- 障がいのある方への介護給付費
主な条例案
札幌市手話言語条例案
手話が言語であるとの認識を普及するため、新たに制定されたものです。手話が独自の言語体系を有する文化的所産であること、また、手話を使用する者が基本的人権を享有する個人として尊重されることを基本理念とし、市の責務や市民と事業者の役割を定めています。
可決された主な意見書・決議(概要)
意見書
意見書とは市政の発展に必要な事柄について、市議会の意思を決定し、国会や政府に提出するものです。
消費者被害を防止・救済する実効的な消費者契約法改正等を求める意見書
高齢者や若年成人などの消費者被害を防止・救済するためには、実効的な法整備が必要であるとして、政府に対し、以下の事項を実施するよう強く要望するものです。
- 消費者庁から平成29年8月に提示された「報告書における消費者契約法の改正に関する規定案」の内容が反映されるよう、今国会中に確実に消費者契約法の改正を実現すること。
- 合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる「つけ込み型勧誘」の類型について、高齢者などの知識・経験・判断力の不足を不当に利用し、過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合の取消権規定を、早急に検討すること。
- 消費者に対して消費者契約の内容に関する必要な情報の提供に努めるべき事業者の義務について、考慮すべき要因となる消費者の事情として、「当該消費者契約の目的となるものについての知識及び経験」のほか、「当該消費者の年齢」など、適用範囲の明確化を検討すること。
決議
決議とは、市議会としての意思を決定し、それを対外的に表明するものです。
財務省公文書書き換え問題について真相究明を求める決議
財務省は、学校法人への国有地売却問題で、14の公文書において、およそ300カ所にも及ぶ大量の書き換えをしていた事実を認めました。この公文書の書き換えは、政府の公文書の信頼性を大きく傷付けただけでなく、議会制民主主義の根幹を揺るがす極めて深刻な問題と言わざるを得ません。よって、政府に対し、この問題について真相究明し、国民への説明責任を果たすとともに、二度と繰り返さないよう、改善策を講ずることを強く求めるものです。
⇒可決された意見書および決議の全文は、意見書・決議のページに掲載しています。
市政を問う!~代表質問から~
8人の議員が、市政について市長などに質問しました。
自由民主党:中川賢一議員
オリパラ招致とウインタースポーツ都市
【Q】オリンピック・パラリンピックの招致を目指すのであれば、札幌でもう一度開催する意義とともに、明確なビジョンに基づくインフラ整備や民間投資の促進、関連産業の育成など、未来のまちづくりの方向性をしっかりと整理し、市民や関係者と共有すべきです。オリパラの開催概要計画では、アジア・世界に誇るウインタースポーツ都市として確固たる地位を築くことが掲げられていますが、そのための取り組みと、最も効果的な招致のタイミングについての考えを伺います。
【A】オリパラ招致を契機に、ウインタースポーツ文化が市民に根付き、さらには世界中からウインタースポーツを楽しむ多くの人々が集まる、世界に誇るウインタースポーツ都市・札幌の実現を目指します。そのために、高度な都市機能と豊かな自然が共存する札幌の魅力を全世界に発信していく考えです。また、招致のタイミングについては、海外候補都市の情勢も勘案し、さまざまな方々の意見を聞きながら結論を出します。
幅広い世代の町内会参加と条例
【Q】町内会は、市民がまちづくりに参加する入り口として地域コミュニティー全体をつなげる役割を果たしてきましたが、加入率の低下や参加者の高齢化・固定化により、その機能が衰退しつつあります。本市では、町内会の意義や重要性などの理念を定める条例の制定を検討していますが、幅広い層の参加やその活動を適正に地域の意思決定に反映させる視点を、どのように取り入れていくのか伺います。
【A】市民との意見交換会や地域活動体験会などを通じ、参加しやすい町内会や地域活動の在り方について、数多くの意見やアイデアを頂きました。「町内会に関する条例検討委員会」では、これらを十分踏まえた上で議論しており、今後も引き続き、幅広い世代の視点を取り入れながら検討を進めます。
災害対応力を強化する総合防災訓練
【Q】昨今、全国的に大規模な自然災害が発生しており、本市でもいつ大きな災害が起きるか分からない状況です。先日開催された札幌市防災会議では、総合防災訓練の見直し検討を進めるとの報告があったと聞いていますが、災害対応力の強化に向け、総合防災訓練をどのように発展させていくのか伺います。
【A】これまでの総合防災訓練は、地震に限定した想定のもと9月の防災週間に実施してきましたが、昨今の状況を踏まえ、今後は風水害なども想定し、災害時期も含め柔軟な訓練ができるように見直しました。さらに、災害対応力向上に向け、より実践的な住民参加の取り組みや関係機関との一層の連携が図られるよう、訓練の内容についても検討していきます。
厳冬期を想定した防災訓練
【Q】本市においては、冬期間に災害があった場合、被害がより深刻になることは容易に想像できますが、そのための防災訓練が極めて少ないと感じています。厳冬期を想定した防災訓練の実施と、備蓄品を含め、より実態に即した対応を検討すべきと考えますが、いかがか伺います。
【A】厳冬期の避難を体験することは自助・共助の観点からも有意義であると認識しており、より多くの市民や職員が参加できる訓練を実施していきます。また、現在も厳冬期の被害想定に基づきさまざまな対策を行っていますが、今後、現状を検証するとともに、市民意見などを取り入れながら、備蓄品の在り方を含めた取り組みを検討していきます。
その他の質問
- 新たなMICE施設の整備
- 待機児童対策
- 医療機関における外国人対応
民進党市民連合(※):松原淳二議員
※民進党市民連合は、平成30年4月1日から会派名の表記を「民主市民連合」に変更していますが、ここでは第1回定例会時点での会派名で記載しています。
将来的な介護保険料上昇への対策
【Q】本年4月を開始年度とする「札幌市高齢者支援計画2018」の案では、団塊の世代が全て75歳以上となる2025年には、要介護・要支援認定を受ける方、サービスを利用する方共に大幅に増加することを見込んでおり、それに伴い本年4月以降の65歳以上の方の介護保険料基準額を増額するとしています。4月以降の保険料については上昇の抑制策を講じていますが、将来的な上昇が見込まれる中、今後どのような対策を講じるのか伺います。
【A】高齢者支援計画2018では、高齢者が自立した日常生活を維持できるよう健康支援などに努めるとともに、要介護状態の方に対しては医療と連携したサービスを提供し、その維持・改善に取り組むこととしています。今後も、予防・早期支援と適切なケアマネジメントの推進により効果的な事業運営に努め、介護保険制度の持続可能性を高めていきます。
介護職員不足の解消
【Q】近年、本市は介護職員不足の状況にありますが、今後、本市の人口が減少に転じる中、少子高齢化がますます進行して生産年齢人口の割合も減少する見込みであり、国も2025年には介護職員が37万7,000人不足すると見込んでいます。このような状況についての認識と、その解消のための施策について伺います。
【A】多くの事業者から人材確保が厳しい状況にあるとの声が上げられており、重要な課題と認識しています。人材不足の解消には、働きやすい職場づくりを進めて介護職員の離職を防ぐとともに、幅広い世代の人材を活用する施策が必要です。そのため、労働環境の向上につながる研修や説明会の開催などに加え、高齢者や主婦などの地域人材の活用の検討、若年層への啓発活動などに取り組んでいきます。
豊平川の河川敷地における雪堆積場
【Q】本市では、都心の雪を処理するため、中心部を流れる豊平川の河川敷地を活用した雪堆積場を設置してきました。しかし、担い手や機材の不足が懸念される中、将来にわたり安定的な除雪事業を行うためには、運搬距離を短縮できるような雪堆積場の確保などを、都心周辺で一段と積極的に行う必要があります。そこで、豊平川の雪堆積場について、夏場の利用者や周辺地域の住民などに配慮しながら、関係機関と連携してさらに拡大する必要があると考えますが、いかがか伺います。
【A】都心周辺には雪堆積場として利用できる土地がほとんどないため、河川敷地などを最大限活用すべきと考えており、今年度は、河川管理者および地域住民と協議して、使用時間などに一定の条件を設けた上で、新たに3カ所で約20万立方メートルの雪堆積場を確保しました。来年度以降も、河川敷地の多くが夏場に利用されている実態を踏まえつつ、拡大に向けた協力が得られるよう、利用者や地域住民、河川管理者などの関係機関と協議していきます。
大規模な融雪槽の整備
【Q】市長の公約である「将来を見越した大規模な融雪槽の設置検討」について、熱源や雪堆積場の配置状況などを踏まえながら候補地を検討していると聞いていますが、整備の見通しについて伺います。
【A】雪堆積場が遠い都心周辺などの排雪作業を効率的に行うためには、都心に近い新川水再生プラザで未利用の下水処理水を活用し、現在稼働中の融雪槽の能力を大幅に増強することが有効です。来年度は基本設計を行い、できるだけ早期に整備したいと考えています。
その他の質問
- 女性の活躍推進に資する子育て環境
- 働く世代のがん患者への支援
- 新さっぽろ駅周辺地区のまちづくり
公明党:小口智久議員
女性活躍の推進に係る考え方
【Q】本市では、離職している子育て中の女性のうち6割以上が就職を希望しているにもかかわらず、有業率が4割と低いことが喫
緊
の課題です。また、女性活躍の推進にはさまざまな面から取り組むことが求められており、複数の関係部局が綿密に連携し、力強く推進していく必要があります。そこで、このたびの予算案における女性活躍の推進に係る取り組みの考え方と、今後の進め方について伺います。
【A】女性活躍の推進は、女性への支援に加え、企業を後押しする環境整備、社会の意識改革という3つの観点から一体的に取り組んでいく考えです。また、今後は、就労や子育てを始めとして、分野横断的に高い成果が得られるよう連携しながら、市民の目線に立って効果的に取り組みを進めていきます。
本市への寄付拡大に向けた取り組み
【Q】本市への寄付には国際交流など12の分野がありますが、「寄付をしても、どこにどのように使われているか分かりにくい」との声が寄せられることがあり、使途をより具体的に示すなど、地域貢献への満足度を高めつつ、寄付しやすい環境づくりに努める必要があると考えますが、いかがか伺います。併せて、寄付のインセンティブ(※)向上に有効な手だてについても伺います。
【A】寄付しやすい環境づくりに向けては、地域に必要とされているものを寄付し、地域に貢献したと寄付者が感じることが重要であるため、使途の明確化や選択肢の拡大に努めていきます。また、寄付のインセンティブ向上には、寄付者の思いとその成果を広く周知することも有効と考えており、寄付物品に氏名を表示するなど、より効果的な手法を検討していきます。
※やる気を起こさせるような刺激、動機付けのこと。
丘珠空港の活性化と騒音への配慮
【Q】近年、丘珠空港の利便性の高さが改めて認識されており、先般報告書が公表された「丘珠空港の利活用に関する検討会議」でも、道外と結ぶ観光や国内ビジネスなどの路線を視野に入れた、一歩進んだ利活用策が議論されています。一方、空港が活性化すると、周辺地域への騒音などの環境影響が今以上に大きくなることが懸念されます。そこで、丘珠空港の活性化に当たり、周辺地域に対する騒音について、どのように配慮していくのか伺います。
A騒音への配慮については、報告書に明記されているとおり、環境基準を超えることのないよう、引き続き騒音調査により状況を把握し、生活環境の保全を図っていきます。
北海道新幹線とトンネル工事の発生土
【Q】北海道新幹線の札幌延伸に向け、本市内でもトンネルの発注見通しが示されるなど、建設事業が本格化しています。しかし、トンネル工事は工期短縮が難しく、計画的に施工することが求められ、そのためには、工事で発生する土砂を円滑に処理することが重要です。また、発生土の有効利用の視点も持ちながら環境に配慮して対応することは、市民理解を深め、着実な建設推進に寄与します。そこで、発生土の取り扱いについて市民理解を得るため、どのように取り組むのか伺います。
【A】本市としては、発生土の取り扱いを担う鉄道・運輸機構に対し、発生土の性質を十分に調査・分析し、適切に取り扱うよう求めています。加えて、市民理解を得るため、ニュースレターやホームページを用いて丁寧な情報提供に努め、2030年度末の札幌延伸に向けて、着実に事業が進むよう協力していきます。
その他の質問
- 子どものウインタースポーツ振興
- 多様なインバウンド受け入れ体制の整備
- SNSを活用した児童生徒の悩み相談
日本共産党:村上ひとし議員
行き場の無い高齢者などへの支援
【Q】東区の共同住宅火災事故(※)に関連し、2015年の厚生労働省調査によると、法的位置付けの無い同様の施設は全国に1,236あり、そのうち本市は195を占め全国最多とのことです。特に本市の場合、高齢者を対象とした施設が8割を超えているのが特徴です。これは、高齢者や生活困窮者に対する住宅施策の貧困の表れだと思いますが、いかがか伺います。また、こうした痛ましい事故をなくすためには、公的支援策を抜本的に拡充する決断が必要だと思いますが、認識を伺います。
【A】高齢者や生活困窮者の安全・安心な暮らしの確保は、非常に大きな問題です。これらの方々の安定した生活と居場所の確保に向けて、支援の在り方を含め、行政としての課題と対策について検討しています。
※2018年1月31日の深夜、東区の「そしあるハイム」で火災が発生し、高齢者や生活困窮者など11人が死亡、3人が負傷した事故のこと。
火災事故防止とケースワーカーの役割
【Q】東区の共同住宅火災事故について、再発防止策を講じるに当たり、保護受給者の生活実態を知り得る立場にあるケースワーカーが作成した記録などを検証し、入居経緯を把握する必要があると思いますが、認識を伺います。また、ケースワーカーが住居を訪問した際に防災上の不備が懸念される場合は、消防局などへ積極的に情報提供すべきだと思いますが、いかがか伺います。
【A】入居経緯については、既にケース記録などを確認し把握しています。また、福祉部局と消防部局の連携は重要であり、これまでも情報共有してきましたが、国でも協議が進められていることから、再発防止に向けて、さらなる情報共有の在り方を検討していきます。
都心アクセス道路整備の費用
【Q】都心アクセス道路を地下構造または高架構造で整備する場合は、新たに札樽道との接続工事なども必要となりますが、建設事業費、維持管理費およびそれらの変動幅をどの程度見込んでいるのか伺います。また、本市の財政状況が楽観視できない中、新たな道路建設による維持管理費の増加は、公共施設の老朽化対策の遅れなどの影響を及ぼし賛成できないと考えますが、いかがか伺います。
【A】建設事業費や維持管理費については、今後、検討が進められる道路構造を踏まえて算出されていきます。なお、検討状況については、進捗
に応じて丁寧に情報提供します。また、老朽化対策については、中長期的な視点で計画的に進めていきます。
都心アクセス道路の効果
【Q】本市は、都心アクセス道路整備により、渋滞の緩和、観光客の利便性向上、物流の効率化などを図り、都市の魅力と活力向上につなげるとしていますが、実態を考えると、その効果は疑問です。また、都心への車の流入を増やすアクセス道路は、人と環境に配慮した総合的な見地から検討すべきと思いますが、いかがか伺います。
【A】本市では、2012年1月に策定した総合交通計画に基づき、公共交通を軸とした交通体系を確立するとともに、適切な自動車交通や、人と環境を重視した都心交通の実現などを目指しています。この中で、都心アクセス強化は、道内の各地域や空港などの交通拠点との広域的ネットワークを強化する取り組みとして位置付けています。
その他の質問
- オスプレイの訓練移転に伴う懸念
- 国民健康保険料の引き下げ
- 既存集合住宅での外断熱改修の促進
改革:堀川素人議員
球団撤退時の札幌ドームの市債残高
【Q】日本ハムファイターズは2023年に札幌ドームから撤退する予定ですが、札幌ドームには多額の借金が残っています。撤退時の借金残高と、その返済期間について伺います。
【A】球団が新球場の開業を予定する2022年度末における札幌ドーム建設費に係る市債残高は、元金約73億円、利子約26億円、合計で約99億円と見込まれ、その返済は2032年度まで続く予定です。なお、北海道からの補助金約26億円が交付される予定であり、本市の実質的な負担は約73億円となる見込みです。
球団撤退後の札幌ドームの経営
【Q】球団撤退後の札幌ドームは、多額の借金返済に加え、新球場という最大の経営ライバルに立ち向かっていかなければなりません。球団撤退の一因と言われている古い経営感覚では、激しさを増す経済変化に対応できず、ドーム経営からの撤退も考慮すべきと考えますが、いかがか伺います。併せて、札幌ドームの経営は新球場建設後も成り立つのか、見解を伺います。
【A】球団の移転はドーム経営に極めて大きな影響があることから、収益構造の抜本的な転換を図るため、新たなイベント誘致に関するマーケティング調査およびその分析を鋭意行っています。今後、新たなスポーツイベントなどの誘致に向け、より具体的な営業活動を行うとともに、経営削減などを含む経営改革案の検討を深めることで、本市の財政への影響を最小限に抑えるよう努めていきます。
その他の質問
- 児童会館特例認定違反事件
- いじめ問題の検討委員会による調査報告
- 東区の自立支援住宅の火災事件
無所属:坂本きょう子議員
義務教育における教材費の負担
【Q】義務教育は無償が前提であるにもかかわらず、教材費などが家庭の大きな負担となっています。義務教育に関する費用は漏れなく全て無償化すべきであり、教材費などの負担軽減を図るべきと思いますが、いかがか伺います。
【A】義務教育では、各学校の判断で活用する補助教材などについて、その負担を保護者にお願いしており、選定に当たっては、指導効果の観点などに加え、保護者負担にも配慮しています。今後も精選を図るなど、保護者の負担が過重とならないよう配慮を促します。
給食費の値上げと保護者の理解
【Q】家庭の経済状況にかかわらず給食を提供することは、子どもの貧困問題の観点からも大変重要です。時代の要請に逆行する給食費の値上げはすべきではなく、保護者の理解は得られないと思いますが、いかがか伺います。
【A】学校給食運営委員会(※)での審議の結果、食材価格の高騰などにより、値上げはやむを得ないとの答申がありました。今後、各学校から丁寧な説明を行い、保護者の理解は得られるものと認識しています。
※学校給食に関する諸問題や、学校給食の運営に関し必要な事項について審議することを目的に、学校長、保護者、学識経験者などで組織される委員会のこと。
その他の質問
- 創成川通の機能強化
- LGBT施策
- 保育所入所に関する運用
市民ネットワーク北海道:石川佐和子議員
重度障がいのある方への訪問介護
【Q】重度障がいのある方への訪問介護は、あらかじめ定められた審査基準で支給量を決定するだけではなく、個別の生活実態をより反映させた非定型の支給決定を導入することが望ましいと考えますが、いかがか伺います。
【A】これまで実施した訪問調査結果などを踏まえ、障がいのある方や学識経験者、事業者などで構成される検討会議を設置し、さまざまな観点からの意見を聞きながら、非定型の導入を含めて支援の在り方について検討します。
補装具費支給事務の迅速化
【Q】障がいのある方への車いすなどの補装具の交付決定にかかる時間短縮に向けて、標準処理期間を定めるとともに、理学療法士や作業療法士など専門家の配置を充実すべきと考えますが、いかがか伺います。
【A】今後は、補装具業者などに対し、理学療法士などの専門家が在籍している身体障害者更生相談所への事前の相談を促すほか、相談所での判定業務を見直すなど、迅速な支給決定に努めていきます。また、標準処理期間の設定については、他都市の状況などを踏まえ検討していきます。
その他の質問
- 多文化共生のまちづくり
- 丘珠空港問題に係る地元住民の声
- 石狩西部広域水道企業団事業
維新の党:中山真一議員
高齢者の移動手段の確保
【Q】高齢化や単身世帯の増加により、通院や買い物などの移動手段確保に困難が生じているとの声を耳にしますが、市の認識を伺います。また、本市には、高齢者の生活支援を主眼とした移動手段の確保について、担当組織も指針となる計画なども存在しません。「誰もが安心して暮らすことのできる街」を実現するためにも、まちづくり部門や福祉部門などが連携し、担当部署をつくるなどの取り組みを本格化すべきと考えますが、見解を伺います。
【A】本市では公共交通を軸とした交通体系を整備しており、日常生活に必要な移動手段はおおむね確保されていると認識しています。しかし、市民に身近な路線バスについては乗務員不足などの課題を抱えており、路線廃止などにより大きな影響が出ることのないよう、最大限努力しているところです。このような状況のもと、今後、高齢者の移動手段の確保に一定の工夫が必要になってくると認識しています。国では「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」で制度の検討を進めており、本市としても、国の動きを注視しながらどのような工夫ができるか研究していきます。
その他の質問
- 除排雪事業の構造改革
- 少人数学級の拡大
- 学校現場と連携した子ども支援
本定例会の議決結果一覧
本会議の結果【平成30年第1回定例会・審議結果】のページをご覧ください。
平成30年度各委員会メンバー
常任委員会
|
総務委員会 |
財政市民委員会 | 文教委員会 |
|---|---|---|
| 企画、都市計画、清掃、環境保全、消防など | 住民活動、市民生活、区役所、文化、財政など | 学校教育、社会教育、子育て支援など |
|
(委員長)林 清治 (副委員長)松井 隆文 三上 洋右 飯島 弘之 北村 光一郎 小野 正美 大嶋 薫 成田 祐樹 福田 浩太郎 田中 啓介 中山 真一 |
(委員長)小竹 ともこ (副委員長)小口 智久 高橋 克朋 小須田 悟士 中川 賢一 福士 勝 ふじわら 広昭 山口 かずさ わたなべ 泰行 池田 由美 坂本 きょう子 |
(委員長)丸山 秀樹 (副委員長)岩崎 道郎 宮村 素子 五十嵐 徳美 長内 直也 こじま ゆみ 峯廻 紀昌 長谷川 衛 竹内 孝代 太田 秀子 堀川 素人 |
| 厚生委員会 | 建設委員会 | 経済観光委員会 |
| 社会福祉、国民健康保険、保健衛生など | 道路、公園、河川、除雪、住宅、上下水道、区画整理など | 産業、観光、スポーツ、市立病院、市営交通など |
|
(委員長)村上 ゆうこ (副委員長)伴 良隆 武市 憲一 こんどう 和雄 宗形 雅俊 畑瀬 幸二 桑原 透 かんの 太一 本郷 俊史 好井 七海 平岡 大介 |
(委員長)伊藤 理智子 (副委員長)阿部 ひであき 鈴木 健雄 細川 正人 村松 叶啓 三宅 由美 小川 直人 中村 たけし 國安 政典 小形 香織 松浦 忠 |
(委員長)佐々木 みつこ (副委員長)松原 淳二 勝木 勇人 よこやま 峰子 村山 拓司 恩村 一郎 しのだ 江里子 涌井 国夫 前川 隆史 村上 ひとし 石川 佐和子 |
議会運営委員会
| 議会運営委員会 |
|---|
| 議会運営上必要な事項に関すること |
|
(委員長)小須田 悟士 (副委員長)峯廻 紀昌 佐々木 みつこ こじま ゆみ 飯島 弘之 桑原 透 林 清治 國安 政典 福田 浩太郎 小形 香織 |
議会事務局からのお知らせ
宗形雅俊議員逝去
札幌市議会議員の宗形雅俊氏(63歳)は、平成30年5月20日に亡くなられました。宗形氏は、平成19年に初当選した後、3期11年余にわたり、市議会議員として市政の発展のためにご尽力されました。この間、総務委員会委員長、文教委員会委員長、建設委員会委員長などを歴任されるとともに、平成30年4月からは、札幌市都市計画審議会委員を務められました。ここに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りいたします。
平成30年第2回定例会審議日程
本会議の結果【平成30年第2回定例会・日程表】のページをご覧ください。
調査特別委員会の中継をスタート
平成30年度から、本会議や予算・決算特別委員会に加え、調査特別委員会のインターネット中継を開始しました。中継は、パソコンのほか、スマートフォンやタブレット型端末でも視聴できます。傍聴できない方も、生中継または録画で会議をご覧いただくことができますので、市議会ホームページから、ぜひ一度ご覧ください。
政務活動費の収支報告書などを公開しています
市議会各会派に交付した平成29年度分の政務活動費について、収支報告書と領収書などの写しの閲覧が始まります(どなたでも閲覧できます)。
閲覧が可能となる日:6月1日(金曜日)
閲覧可能日時:午前8時45分~午後5時15分(土曜、日曜、祝休日を除く)
閲覧場所:市役所本庁舎(中央区北1条西2丁目)15階議会図書室
政務活動費とは?
地方自治法第100条第14項から第16項までの規定により制定された「札幌市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、札幌市議会における会派または所属議員が行う調査研究、研修、広報広聴、市民相談、要請陳情、会議への参加など、市政の課題および市民の意思を把握し、市政に反映させる活動ならびに市民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費の一部として、議会における会派に対して、次のとおり交付されるものです。
対象
会派(所属議員が1人の場合を含む)
金額
月額40万円×各月における当該会派の所属議員数
交付方法
4月、7月、10月、1月にそれぞれ3カ月分を交付
※各会派は、毎年度その収入・支出の状況を支出の科目(使途)ごとに報告することになっています。
※年度末において残額があった場合は返還します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.