ここから本文です。
さっぽろ市議会だよりNo.138
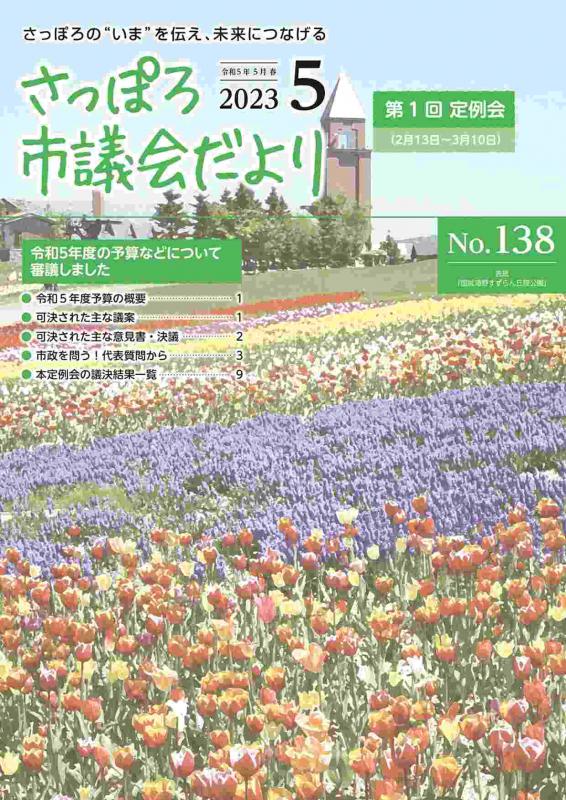
PDF版
| 主な内容 | ページ |
|---|---|
| No.138(令和5年5月春号) | 全ページ(PDF:2,826KB) |
|
令和5年度予算の概要 可決された主な議案 |
1ページ(PDF:384KB) |
|
可決された主な意見書・決議 |
2ページ(PDF:482KB) |
| 市政を問う!代表質問から | 3~8ページ(PDF:3,696KB) |
| 本定例会の議決結果一覧 | 9~10ぺージ(PDF:798KB) |
| 議会事務局からのお知らせ | 11ページ(PDF:421KB) |
音声版さっぽろ市議会だより
音声版さっぽろ市議会だよりNo.138(YouTubeに移動します。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.